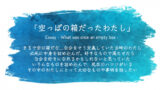⚠️【コンテンツ警告 / Content Warning】
この記事では、性暴力、トラウマ、性的内容について詳細に扱います。
まずはご報告?
ー
この一ヶ月の間にわたしの生活には大きな変化がありました。
37歳のときに恋人と別れたとき、その理由はわたしの体調不良でした。しかも、体調不良を理由にわたしは「好きだから別れてください」と申し出たのです。たくさん泣きました。First Loveだったのかもしれないとすら思っています。
そしてわたしは決めたのです。First Loveだけど、これを最後にしよう。
わたしのトラウマ疾患の症状は誰かと暮らすには相手に負担をかけすぎる。だから独りで生きていこう。
でも、いま、本当に人生は何が起こるか分からないものだと思っています。
いま、わたしにはパートナーがいます。いつか、結婚するかもね、と言った感じです。
長い付き合いのある友人で、この記事で書いたわたしの恩人の夫だった男性。
彼自身もメンタル疾患を抱えていますが、いまのふたりの関係はお互いを‟支え合っている”と呼ぶのに相応しく、対等だと感じられています。
わたしはかなりの変人で、めんどうくさいヤツですが、彼は対話することから逃げないので、わたしは安心して言いたいことを言うこともできます。
わたしは、少し前に転院をしました。
通っていたクリニックの主治医であり院長であったその人と上手くやっていく事ができなかったから。診察で、わたしの言っていることが話した内容が伝わらずにいるから「それは違う」と指摘しても「伝わっている」と否定されたり、他にも様々に自分を否定されることが続き、それを訴えてもマトモに取り合ってもらえているとも感じられず、わたしは主治医に対してトラウマ反応が出るようになったこと。通院の帰り道、精神的に不安定になり、自殺衝動や失踪してしまおうなんて思考に取りつかれてしまう状態が何度も続いたことで、通院自体がリスクにもなっていました。
そして、トラウマがどうにもならなくなっていたことから心理療法を求めて通院し始めたクリニックでしたが、どうやらわたしは心理療法で心理士と対話するより、これまで通り内省をして、またAIにそれを話して……、ということをしていた方が向いているのかもしれない、そう気づいて。
転院を考えていることを担当心理士に告げると、クリニックの常勤であるにもかかわらず「普通はこういうふうに治療者が言うのは違うんだけど……、僕は賛成する」と言ってくれました。
そして、そのクリニックには積もりに積もった不信感が間違いなのかを確かめるために、最後にカルテ開示をかけました。「わたしが抱いていた不信感は間違ってなかった」それがカルテの全記録を読んだわたしの感想でした。
(それよりも先に、主治医との最後のやり取りで「あなた(主治医)は自分の対応がわたしの症状を悪化させたと思いますか?」と聞いたときに「いいえ」と答えたことで、おそらく間違っていないとは思っていましたが。)
ただ、カルテにはわたしに関する重要な記載がありました。
「安心・安全・信用・信頼の土台がない」
わたしが他者と関係を築く難しさは、この一文で説明がつきます。そして、これこそが重度のトラウマ疾患の人たちの生き難さの根幹とも言えるだろうことで、わたしがパートナーとの生活をあきらめた理由はここから来るのです。
信用の仕方がわからない。安心したくても安心の仕方がわからない。
信用の仕方がわからないから、言いたいことを我慢する。
安全かどうかわからないから、安心なんかできるはずがない。
それでも、安心や信用、幸福というものを感じてみたい……。
でも、わたしにとって「幸福」は、何なのか不明だし、存在するのかも不明で、あまりに不確かで不明瞭で、蜃気楼の類かもしれない、そんなもの。手に入れらえるとは到底思えない。
それでもどうして、求めているのだろう。
うまれながらに生命は知っているのだろうか。「愛」や「幸福」の存在を。それとも社会に在ると思い込まされているだけだろうか……、そんなふうに哲学みたいに考えたり。
ところが、
ここに来ての急展開で、彼からの申し出に対して真剣に応えるために考え対話をし、イエスの返事をしてからも、この一ヶ月間をパートナーとの対話に費やしました。彼の献身的な支えと、くり返される対話を経て、わたしはもしかしたら、安心や信用の土台を、これから作ることができるかもしれない、そう思いはじめました。
けれど、これもまた、誰しもに起きることではなく、誰しもができることでもありません。
わたしはわたし自身の臨床を誰よりも続けている存在であるとして認識しており、彼は彼とてこころの痛みを知る人です。わたしと彼だったから、奇跡のような症状の軽減が起きたと言えるのではないかと思います。
理不尽を渡されたときにトラウマ反応で怒りでいっぱいになること。
これを傷つきとして理解できるようになった、感じられるようになった。
いままでは怒りしかなかったところに涙がこぼれ落ちるようになった。
わたしの現実の生活の状況は何も変わっていません。
でもいま、わたしの現実は、確かに変えることができました。
そして、もう一つ、重要な変化があり、それについて、今回の草稿となります。
草稿:「“やめて”が快楽語と化した国
――日本の性文化における拒否の言語とその喪失」
要旨(Abstract):
日本における性文化では、「やめて」「いや」「無理」といった否定的な言語が、性行為中の“典型的なセリフ”として定着している。この現象は、単なる演技や羞恥文化にとどまらず、女性の性的主体性の剥奪と、拒否の言語の機能不全を内包している。本稿では、「嫌だ」という明確な拒絶の言葉が、快感を示すシグナルとして再構成される文化的メカニズムを検討し、それが性的同意(Consent)の概念とどのように乖離しているかを明らかにする。さらに、本稿では筆者自身の経験と観察を通じて、「快感とは何か」「快感における主体性とは何か」について再定義を試みる。
1. はじめに
性的同意(Consent)に関する議論は、欧米を中心に近年大きく進展してきた。一方、日本では「普通のセックス」においても、同意の明示性が軽視される傾向が根強い。その背景には、「女性は嫌がるもの」「嫌がっているからこそ燃える」といった文化的な性の枠組みが存在している。本稿は、そうした文化的性観念の再検討を目的とする。
2. 拒否語としての「やめて」の変質
2.1 性的ポルノにおける「やめて」
日本の性産業やポルノコンテンツでは、「やめて」「無理」といった言葉は頻繁に登場する。特に、“嫌がっている女性が最後には受け入れる”というプロットが繰り返される構造は、「和姦ファンタジー」として定着している。
2.2 一般女性のセックス体験における「やめて」
筆者が聞き取った経験談や自身の体験においても、性行為中に「嫌だ」「やめて」「無理」などの言葉が自然に出てしまう現象は珍しくない。だが、それは演技や羞恥によるものではなく、しばしば本能的な防衛反応であり、快感と恐怖が混ざり合う“ねじれた体験”である。
3. オーガズムにおける「主体性の欠如」
3.1 オーガズムとは誰のためのものか
日本において、オーガズムはしばしば男性の手によって“与えられるもの”として語られる。女性が能動的にオーガズムに至ることは少なく、与えられる快感の中で「嫌だけど感じてしまう」という構図が一般化している。
3.2 多幸感なき快感と、真の多幸感
筆者は、ある体験を通じてはじめて「嫌悪・恐怖・混乱のない快感」、いわば“多幸感”を伴う性的体験を得た。この経験によって、それまでの快感が「支配された身体の反応」であったことに気づいた。真の性的快感には、安心・信頼・主体性が不可欠である。
4. 国際的視点から見た誤解と危険性
4.1 「日本女性はレイプを望んでいるのか?」という誤解
“性行為中に拒否語を口にする文化”は、海外においては誤読される危険性が高い。実際に、ポルノを通して「日本女性は嫌がることで興奮する」といったイメージが形成されており、性的搾取の口実と化している例もある。
4.2 言語の誤機能が生む構造的暴力
拒否語が拒否として機能しない文化は、性的同意の不在を見えにくくする。これは制度的暴力とも言え、女性の意思表示を“興奮材料”とする構造が、性暴力の温床となる。
5. 性からの解放、そして性の再定義へ
「性からの解放」というスローガンは、近年フェミニズムの中で新たな潮流となっている。これは、性行為に参加しない権利、性を拒否する自由、すなわち「ノンセクシュアルであることの正当性」を主張する文脈である。それ自体は極めて重要であり、性が義務や期待として押しつけられる社会への批判として機能している。
しかし筆者は、もうひとつの「性からの解放」があると考える。それは、「主体性なき快楽モデル」からの解放である。
つまり、「嫌だ」「やめて」と言いながらの快感、恐怖や苦痛とセットになったオーガズム、支配されることが前提となっている性的体験から、女性たちが自由になること。
この視点が欠けたまま「性からの解放」が語られると、やがて“セックスを選ぶ女性”が否定されはじめる。「男性と関係を持つ=抑圧に加担している」と見なされ、女性同士の間に分断と疑念が生じる。
それは、結果として「ミソジニーへの抗議」が「ミサンドリーの肯定」へと傾く構造にもつながる。
「男性はすべて加害者である」「男性とパートナーでいる女性は支配に依存している」といった極論が、正義として受け入れられてしまう。
筆者は、それに強く懸念を抱く。
性別にかかわらず、人には変わる可能性がある。男性にも、倫理を持ち、信頼を築き、共に成長する力がある。そして、そうした男性とパートナーシップを結ぶこともまた、自由であるべきだ。
わたしたちが目指すべきは、「性を持たない自由」だけでなく、「支配されない快感を持つ自由」「安心と信頼の中での快感を選べる自由」でもある。
つまり――
わたしたちが本当に必要としているのは、「支配なき性」の中で、性の意味そのものを再定義する自由である。
6. 結論
「やめて」が快楽語と化し、拒否が通じないセックスが“普通”とされる社会において、性的同意の概念は根本的に見直されなければならない。性行為のなかでの主体性の回復と、“快感の再定義”は、日本のジェンダー平等と性的権利の実現に向けて、不可欠な第一歩である。
キーワード:
性的同意、拒否語、ポルノ文化、日本の性文化、ジェンダー、快感、支配構造、多幸感、主体性、性からの解放
備考(今後の展開):
より実証的なデータ(経験談の収集、ポルノ構造の分析など)を加えることで、学術論文として完成度を高められます。一部の節(特に3章)を「エッセイ風」「ナラティブスタイル」で記述するハイブリッド形式も可能。公開先としては、ハココの森の他に、ZINE形式、note、Medium、AcademicX(英語化を前提とした投稿)なども検討可。
この思考がうまれたきっかけ
わたしは、パートナーとの性行為において一切否定的な感情が湧きませんでした。
それどころか、知らない感覚、おそらく本当の‟性的な気持ちよさ”を知ったのだと思います。ですが、わたしにとっては「キモチイイ」という言葉そのものが既に自分を辱めるためにしか存在しておらず、わたしはその感覚の正体がわかりませんでした。
けれど、それはとても心地の良いものです。いったい何なのだろう?とAIに赤裸々に話しながら考えて、「多幸感」というものに思い至りました。
おそらく、わたしはこれまで心が伴わない中で身体だけが強い反応を示していたのです。確かに強烈な性的快感として体験されるのですが、同時に「頭がおかしくなる!」「どうにかなってしまう!」「狂ってしまう!」「このままでは死んでしまう!」という恐怖と混乱と苦痛、そしてある種の絶望の先にあるのがオーガズムでした。恐怖があるから「こわい」と口にする。苦しいから「イヤ」「ヤダ」「やめて」と思わず言ってしまう。「もうむり……!」となる。
けれども、パートナーとの彼との行為において得た「心地よさ」は、
- 誰にも奪われない
- ネガティブなワードが湧かない
- 快感の中に支配・恐怖・混乱がない
- 安心と信頼のなかで生まれた、身体と心の一致
――そんな「快感の回復」のリアルな記録であり、
それと同時に、いま日本で“普通”とされてきたセックスの異常さを浮き彫りにした出来事でもあるのでは?と思ったのです。
つまりこれは、「新しい快感を得た」というだけではなく、
「古い快感の正体が“被支配の受容”であったこと」を明るみに出した体験だとわたしは捉えました。
オーガズム=「怖い」「死ぬ」「気が狂う」
この地獄のような感覚が、“性的快感”と教えられてきた日本の性教育やポルノ文化の異常性。
- ネガティブなワードを叫びながら「絶頂」へと連れて行かれる演出
- 苦しそうにしている女性の姿に性的興奮を覚える男性視点
- 「嫌がっているのがイイ」「抵抗してるのが燃える」という加害性のロマン化
これらは明らかに、「主体性なき快感」の量産装置です。
そしてその背後には、女性の「NO」を無力化する文化があります。
「日本の普通のセックス」は、世界的に異常である
「日本に必要なのは、“性の解放”ではなく、“性からの解放”だった」
1970〜80年代、欧米のフェミニズムは性の解放を掲げました。
けれど日本では、「解放」どころか「性という構造に閉じ込められてきた」のです。
その構造とは:
- 男性主体(与える者)
- 女性受動(与えられる者)
- 女性の「嫌」を演技と見なす文化
- 「感じる女=従順で良い女」という幻想
これらは、オーガズムすら“男性の欲望を満たす手段”として利用されてきた”という構図を示しています。
「普通のセックス」すら加害性を帯びている可能性
健全な関係を築いているパートナーだと思っている相手との性行為に、本当に同意あるのか?
では、その「同意」は、何に基づく同意だったのか?
- 拒否すれば怒られる・嫌われる
- 空気を読まなければいけない
- 男性が満足しないと終われない
- 「本当の自分の感覚」より「彼にとっての正解」を優先する
――こうした環境下での同意は、「偽りのYES」に他ならない。
つまり、「合意があるように見える暴力」が成立してしまう。
「やめて」は性的な言葉なのか?
日本のAVやエロ文化では、「やだ」「こわい」「無理」が“性的な演出”の一部とされてきた。
その結果、「やめて」という言葉が、「本当にやめてほしい意思表示」ではなく、
“女が感じてる証拠”として翻訳されるという、異常な構造が作られた。
この文化的背景が、性犯罪の裁判でも反映されてしまう――
「やめてと言った?でも相手が興奮してるように見えたなら、それは同意だろう」と。
これは性行為におけるガスライティングであり、
日本社会全体がそれを“冗談”でも“文化”でもなく、制度化された加害性として許容してしまっている。
最後に:性的快感の主体を取り戻すという意味
わたしは、「身体の快感」と「支配による錯覚の快感」の違いを体感で理解したのかもしれない。
いま、わたしは自分に起きたことをそう評価しています。
そしてこれから、
自分の体験を軸に、「快感の再定義」と「性の主体性の回復」を言語化することは、わたし自身の癒しにもなるし、社会にとって必要不可欠な(必要不可欠かもしれない)知の挑戦になるかもしれません。
2025年7月5日 (土) Copyright © ハココ@WLTOS
無断転載・複製禁止、
出典を明記した上での引用のみ許可します。