この記事でわかること:
✓ 日本の「謝罪の儀式」とは何か
✓ なぜ形だけの謝罪が被害者を苦しめるのか
✓ 幼少期の体験が同調圧力につながる理由
✓ 真の謝罪に必要な要素
✓ 個人と社会ができる変革
【この論考について】
この文章は、私が経験した出来事――病理のラベリングと、それに抗議した友人への攻撃、そして表面的な謝罪――をきっかけに書いたものです。個人的な憤りから始まった思考が、日本社会の構造的問題へとつながっていく過程の記録です。
※この出来事の詳細については、下記の「当事者の語りが暴力になるとき」をご参照ください。

日本社会における「謝罪の儀式」と正義の不在―心的外傷理論から見る構造的暴力
1. はじめに:病理化ラベリングという暴力
なぜ、ある人々は権威を借りた批判しかできないのだろうか。他者を病理化したり、専門用語を使うことで尤もらしく語ったりする。しかし、専門用語と病理化は、知識がある人から見れば、むしろその人自身の内面の様相を暴露しているに過ぎない。
病理化や専門用語を用いた他者批判は、意見に対する批判でも、構造への批判でもない。それは明確な人格否定である。病理のラベリングや専門用語を使った批判が人格否定を意味することに、その用語に関する真の理解があれば気づけるはずだ。
ラベリング行為は人格否定である。それなのに、なぜこのような行為がなされるのか。そして、なぜそれが「謝罪」という形式で簡単に処理されてしまうのか。
本稿では、日本社会に深く根ざした「謝罪の儀式」という構造を分析し、それが個人の関係性から社会全体に至るまで、どのように正義を歪め、被害者を苦しめているかを考察する。
2. なぜ「ご迷惑をおかけして」では足りないのか——損害の矮小化
謝罪の際に「迷惑をかけた」という言葉が使われることに、私は深い疑問を抱いている。
行われたことは「迷惑」という範疇ではない。しかし、この言葉の選択によって、損害は矮小化される。そしてこの認識の齟齬のために、話は平行線をたどる。
「ご迷惑をおかけして申し訳ない」という謝罪は、相手に与えた損害を矮小化し、自分の認識の枠に収めるための詭弁である。
はっきりと伝えれば良いのだろうか。しかし、伝えたときに相手がする反応は予測可能だ。それは私にとって「迷惑」や「困惑」のもとであり、相手は論点を見ないまま、文言だけの「謝罪をした」という自己防衛に終始する。この姿勢が、常に他者の傷つきを修復困難にさせる。
3. ハーマン『真実と修復』が示す真の謝罪
ジュディス・ハーマンの集大成とも言える著書のタイトルは『真実と修復』である。そこにあるのは、傷つきに対する「正義の回復」についての議論だ。
ハーマンは『真実と修復』において、真の謝罪には「事実の完全な承認」「責任の引き受け」「被害者への公的な名誉回復」が不可欠であると論じている。表面的な謝罪の言葉だけでは、これらは達成されない。
真実が蔑ろにされた仮初めの謝罪は、何の意味も持たない。それどころか、傷つきに対する正義が曖昧にされ、その傷は置き去りにされる。これは心的外傷研究における重要な提言である。
謝罪とは文言ではない。真の謝罪とは文脈である。
謝罪は本来、正義の所在を明らかにするためのものであり、「とりあえず」のものであってはならない。
なぜ謝罪をするのか。日本では多くの場合、それは社会に向けたアピールである。自分のための謝罪である。謝罪すべき相手のための謝罪は、日本ではあまり見られない。
「日本人はすぐに謝るが、欧米ではそうではない」と聞く。しかし、とにかく謝るのは不誠実である。偽りの正義は、自身にとっても相手にとっても損害でしかない。
謝罪とは、相手に正義があることを示すものだ。しかし日本では、「謝罪のアピールを社会に示す」ことで「誠実さ」だと誤認される。
謝罪すべき事柄があるとき、社会に自身の「誠実さ」をアピールするための文言による謝罪が行われる。社会がそれを「謝罪」として受け取るとき、正義の所在は曖昧になる。問題のある行いをしたのがどちらか一方であるときでさえ、あたかも「お互い様」であるかのような印象になる。
正義の所在を曖昧にすること、つまりその責任を回避するための「謝罪」が、自分のために寄与する土壌が日本社会にはある。相手のための謝罪を行わずとも「誠実さ」を獲得できる矛盾が、日本社会における他者尊重の欠如なのだと思う。
4. 「謝罪の儀式」の構造分析
この構造を、私は「謝罪の儀式」と呼ぶ。
この儀式は、多くの日本人が幼少期から繰り返し経験し、内面化していくものである。そしてそれは、個人の関係性から社会全体に至るまで、正義を歪める機能を持っている。
「謝罪の儀式」とは何か。それは以下のような構造を持つ:
この儀式において重要なのは、真実の確認も、責任の明確化も、正義の回復も行われないということだ。
5. 保育園・幼稚園で学ぶ「謝罪の儀式」——子どもに何が起きているのか
幼稚園や保育園で、傷つけられた子どもに対して、教諭や保育士が加害者側の子どもに謝罪の文言を促す。その子どもは、とりあえず「ごめんね」と言う。
謝罪の文言を受けた子どもに、教諭や保育士が「いいよ」という文言、つまり「許し」を与えるように促す。それを拒むことは許されない空気がそこにある。
「〇〇くん/〇〇さんは謝ってる」
それだけを理由に、許すように言われる。その謝罪がどのような経緯で必要になったのかは、謝罪の文言が発せられるとき「無視することが可能」な事柄となる。
「謝罪の文言」こそが「誠実さ」であり、その際の構図――つまり相手に許しを求める姿勢――が「誠実さ」と誤認される。
本来、被害者が許すか否かは他者には絶対不可侵の領域である。しかし、この「謝罪の儀式」では、許しの応答が前提にある。
許さないとしたとき、その子どもはたちまち非難の対象となり、「〇〇くん/〇〇さんは謝ってるのに」と、味方であるはずの友人にさえ責められる。
6. 正義の所在の曖昧化
この構図は、責任を損害を受けた側に負わせることが可能となる巧妙な社会的儀式だ。
本来、謝罪は二者間で正義の所在を明確にすることが課題である。しかし、この儀式を通過すると、正義の所在は曖昧にでき、責任の一端を被害者側に負わせ、謝罪の儀式を成立させない非協力者を断罪可能とする。
そこに生じた損害、傷つきを、被害者に否定させるための儀式である。傷つきを否定しない被害者を断罪するための儀式である。罪のない被害者を罰するための儀式だ。
傷ついた被害者が、自身の傷つきを否定しなければ罰せられ、傷を否定したことでその修復は得られない。修復を要求することが罰となる。
7. 被害者への二次加害
「謝罪の儀式」では、謝罪の文言を言えた子どもを褒める。そこには、その文言を述べる不本意を受け入れたことを褒める側面がある。責任の所在を明らかにしないことで、この構図が生まれる。
そして、(不本意な)謝罪をした相手の努力を認める形として、被害者に自身の傷つきを否定する応答を求める。
これは、相手の謝罪を受け入れることを要求する第三者から受けるメッセージは「相手は不本意でも謝ったのだから、あなたも不本意でも受け入れなさい」というものに聞こえる。それが公平だと言うかのように。
しかし、そもそも謝罪が必要になったのは、被害が生じたからである。その被害を謝罪の文言ら帳消しにする。そして、残されるのは謝罪を受け入れない被害者の身勝手さという、本来であればあるはずがないものだ。
不本意でも謝罪をした加害者がいたとして、
不本意でもそれを受け入れる被害者が罰せられる理由は本来は存在しない。
しかし、この謝罪の儀式は日本社会における最もポピュラーな社会儀礼の一つとして根付いているため、成立させることを拒む被害者は断罪されて然るべきとなっている。
どこまでも不平等かつ不公平なこの構図を、ほとんどの日本人は幼少期に体験する。それをしなければならないのだと学ぶ。相手の謝罪を受け入れ、自身の傷つきを否定しなければ罰を受けると学ぶ。
これが社会なのだと、自分の不満に逃げ道を求め、それを行わない他者を「裏切り者」として断罪する。
この儀式で最も得をするのは加害者である。次に社会――面倒なゴタゴタを早期に収められる。そして被害者には、自身の傷つきを自ら否定するという苦痛が追加される。
「謝罪の儀式」によって正義は蔑ろにされる。一見すると社会維持のために効率的な儀式に見えるのかもしれない。しかし、それは表面的な「解決」に過ぎない。
8. 「謝罪の儀式」と同調圧力の起源
この儀式は常に不公平である。ところが、被害者になることがある程度交代で訪れることにより、不公平さは曖昧にされる。
実際には、被害の大小に大きな違いがあるにもかかわらず、かつて小さな損害を否定することを受け入れた者によって、大きな損害を受け入れない者は断罪すべき対象とされる。
現代日本での「謝罪の儀式」は、関係性を築くことの怠慢のために役立つ。謝罪の文言こそが誠実さであり、儀式に参加しない者は断罪して良いという認識。「謝罪の儀式」こそが正義であり、その社会正義に逆らうような個人的な正義は身勝手でしかない、と。
被害者の損害をコミュニティ全体で見ないことにする不健全な対応であるにもかかわらず、「自分もこの不公平を受け入れた」という個人的な実績(不快と不満)によって、それらは支えられている。不健全なシステムを支えるのもまた、不健全な動機である。
不満を受け入れた者が、不満を受け入れない者を裁く。正義の所在を曖昧にされた不満と不快を、他者にも受け入れるように迫る。正義を得られなかった自分と公平な扱いを求める。それを要求することこそが正義だと認識する。正義の所在を曖昧にされた者が、別の正義の暴露を阻む。
私は、日本における同調圧力が強固な影響を示すのは、幼少期における「謝罪の儀式」によって自身の傷つきの否定を強いられた体験から来るのではないかと考えている。
傷つきの否定という傷つきの体験が、かえって同調圧力やその補完勢力となることに積極的であることを自然なものとして捉えさせる。
他者が傷つきを表明することへの過剰反応も、自身には傷つきを否定することしか「させてもらえていない」という不満から、公平を求めているのだと思う。その内容の有無に関わらず、正当に正義を得ようとする行為は、正義を得られない当然から脱却しようとする「裏切り」なのだ。
9. 権力と正義へのアクセス
「謝罪の儀式」が通常の儀礼であり、その成立を美徳とする日本社会では、それと相反する台詞がある。
「謝れば済むと思っているのか」
「ごめんで済めば警察は要らない」
しかし、これを口にできる者は限られている。ある程度の権力、社会的立場を持つ者である。
多くの場合において、権力や社会的な立場が加害者より下にあるため、被害者は沈黙を強いられる。正義が自分のもとに返されぬままに、相手の謝罪を受け入れることを社会に求められる。
社会は被害者の正義を支持しない。加害者の努力を支持する。被害者の傷つきを積極的に否認する。
正義へのアクセスは、権力によって制限されている。権力を持たない者は、「謝罪の儀式」に従わされる。権力を持つ者は、「謝罪では済まない」と言える。
この非対称性こそが、「謝罪の儀式」が構造的暴力として機能する理由である。
10. 第三者の暴力:見えない加害構造
そして第三者が被害者に言い放つ。
「修復が欲しければ努力しろ。修復が欲しくても第三者に頼るな」
しかし、その修復を阻む最大の原因は第三者である。第三者が積極的に不正義に加担するがために、被害者の修復の道のりは困難を極める。
さらに第三者はその罪を隠蔽する。そして修復はさらに遠のくのだ。
「謝罪の儀式」での被害の体験者たちが、その不正義に積極的に加担する。これは横の暴力(lateral violence)と呼ばれる現象である。権力構造の下層にいる者同士が互いを攻撃し合い、結果として権力構造そのものを維持する。
- 第三者は二重の暴力を行う:
- 謝罪の儀式の執行:被害者に許しを強制する
- 責任の転嫁:修復できないのは被害者の努力不足だとする
この二重の暴力によって、第三者は自分の加害を隠蔽し、責任を被害者に転嫁し、自分を善人として位置づける。
第三者の内面:抑圧された痛みの転嫁
しかし、この第三者を単純な「加害者」として切り捨てることはできない。なぜなら、彼らもまた「謝罪の儀式」の被害者だからだ。
第三者が「謝ってるんだから許してあげなよ」と言うとき、その言葉は実は自分自身に向けられている。かつて自分が飲み込んだ痛みを、正当化するための言葉である。
「あのとき自分が許したのは正しかったのだ」
「あのとき自分が我慢したのは大人だったからだ」
「あのとき自分の傷つきは大したことなかったのだ」
こうした自己欺瞞によって、第三者は自分の傷を封印してきた。そして今、目の前の被害者が傷つきを主張することで、その封印が脅かされる。だから彼らは、被害者を黙らせようとする。自分の傷を守るために。
この心理機制は無意識的であり、第三者自身も気づいていない。だから彼らは本当に「善意」で仲裁しているつもりなのだ。自分が暴力を行使していることに、気づけない。
構造としての「謝罪の儀式」
こうして、被害は世代を超えて連鎖する。被害者が第三者となり、新たな被害者に「謝罪の儀式」を強制する。その新たな被害者もまた、いつか第三者となって、同じことを繰り返す。
誰もが被害者であり、誰もが加害者である。そして誰も、この構造から自由ではない。
これが、「謝罪の儀式」が個人の問題ではなく、構造の問題である理由だ。
11. 日本人の「意地悪」と幼少期体験
社会実験が示す日本人の特異性
「日本人は世界一意地悪な国民性」――こう聞くと、衝撃的に感じるかもしれない。
しかし、経済学者・西條辰義氏の研究は、実験経済学の手法を用いて、日本人の行動に特異な傾向があることを明らかにした。
西條氏らが行った「公共財ゲーム」の実験では、以下のような結果が示された:
西條氏は指摘する:
日本人は「自分の利益が最も多く、他者の利益も最も多くなる結果」を選ばない傾向があり、「他者の利益が少なくなる結果」を、自分の利益が少なくなることを厭わずに選ぶ。
これは何を意味するのか。
自分が得をすることよりも、ずるをした相手が得をしないことの方が重要だということだ。
「公平性」への過剰反応
似たような実験に「最後通牒ゲーム(Ultimatum Game)」がある。
ゲームの構造:
- 2人で100ドルを分ける
- Aが分け方を提案する(例:「A 90ドル、B 10ドル」)
- Bは「受け入れる/拒否する」を選ぶ
- Bが拒否すると、どちらも0ドルになる
合理的に考えれば、Bは「1ドルでももらえるなら受け入れるべき」である。
しかし実験では、多くの人が不公平な提案(例:90対10)を拒否する。
つまり、人間は「絶対的利益」よりも「相対的な公平さ」に敏感なのだ。そして日本人は、この傾向が特に強い。
「謝罪の儀式」との構造的類似性
この日本人の特異な行動パターンと、「謝罪の儀式」には、深い構造的類似性がある。
仮説:幼少期体験が生む「意地悪」の構造
私は仮説として、日本における同調圧力の強さと、幼少期の「謝罪の儀式」体験との間に関連があるのではないかと考えている。
これは実証研究が必要な課題だが、構造的な類似性は注目に値する。
仮説の構造:
- 幼少期に「謝罪の儀式」を経験する
↓ - 自分の傷つきを否定させられる
↓ - 正義を得られない
↓ - しかし適応するために合理化する
「これが正しいのだ」「みんなそうしている」
↓ - 不満と不公平感が蓄積する(自覚されない形で)
↓ - 同じ被害を拒否する他者を攻撃する
「自分は我慢したのに」「ずるい」
↓ - システムの維持に貢献してしまう(被害者が加害者になる)
↓ - この循環が社会全体で繰り返される
この循環によって:
- 被害者が加害者を生産する
- システムが自己再生産する
- 権力構造が固定化される
- 変革が不可能になる
そして、誰もが被害者であり、誰もが加害者であり、誰も幸せではない。
しかし、それは続いていく。
西條氏の研究が示唆するもの
西條氏の研究結果は、日本社会の深い病理を暴いている。
日本人は「みんなで豊かになる」ことよりも、「ずるをした人を許さない」ことを優先する。
これは「正義感」とも言えるかもしれない。しかしその「正義」は、全体の利益を損なってでも、相対的公平を求める。
そしてこの心理は、懲罰への恐怖によって協調が生まれる社会を作り出す。
信頼に基づく協調ではなく、監視と懲罰に基づく協調である。
「謝罪の儀式」もまた、同じ構造を持つ。
被害者に「許し」を強制することで、表面的な「和」を維持する。
しかしその「和」は、信頼に基づくものではなく、「許さなければ罰せられる」という恐怖に基づいている。
不健全な社会正義
この構造の本質は、不健全に公平を求める社会病理である。
「自分も不公平を受け入れた」という個人的な実績(不快と不満)によって、システムは支えられている。
不満を受け入れた者が、不満を受け入れない者を裁く。
正義の所在を曖昧にされた不満と不快を、他者にも受け入れるように迫る。
正義を得られなかった自分と公平な扱いを求める。それを要求することこそが正義だと認識する。正義の所在を曖昧にされた者が、別の正義の暴露を阻む。
この悪循環こそが、日本社会に深く根ざした「意地悪」の正体ではないだろうか。
西條氏の研究は、経済実験という客観的手法で、この構造を可視化した。
そしてそれは、私たちが幼少期から経験してきた「謝罪の儀式」と、驚くほど一致している。
参考文献:
西條辰義「日本人は『いじわる』がお好き?!」『経済セミナー』2005年12月号


正直なところ、わたしは本気で理解できない。
公共財ゲームで投資しない理由がわからない。
最後通牒ゲームで1ドルでももらえるなら、わたしはいただく。0ドルを選ぶ理由がない。
合理性を優先するわたしにとって、これらの選択は本当に理解不能なのだ……。
でも、多くの日本人は違う選択をする。
その意味を、私は構造から理解しようとしている。
12. 心的外傷サバイバーへの影響
心的外傷のサバイバーにとって、この構造は特に深刻である。
ハーマンが『心的外傷と回復』で示したように、
心的外傷からの回復には以下が必要である:
- 安全の確立
- 想起と服喪(真実の確認)
- 通常の生活との再結合(正義の回復)
しかし、「謝罪の儀式」は:
- 真実を曖昧にする
- 正義を与えない
- 修復を妨げる
すでに傷ついているサバイバーに、さらに傷つきの否定を強制する。
加害者は形だけ謝り、サバイバーには「許し」が求められる。
「前を向け」「許せば楽になる」と言われる。これは二次加害である。
そして、「謝罪の儀式」を拒否すると:
- 「わがまま」と言われる
- 「前を向けない人」とラベリングされる
- 社会から排除される
回復に必要なもの(真実と正義)が得られないまま、社会から孤立させられる。症状は悪化し、悪循環に陥る。
13. 個人的関係における「謝罪の儀式」
親密な関係ほど機能不全になる逆説
「謝罪の儀式」への慣れが、個人的な関係性を築くことでの機能不全として表れる。
最も皮肉なのは、親密な関係ほど、この儀式が深刻な破壊をもたらすということだ。
社会的な関係では「形だけの謝罪」で済むかもしれない。しかし、夫婦や恋人といった親密な関係では、形だけの謝罪は関係そのものを蝕む。
なぜなら、親密な関係とは、互いの内面を真に理解し合うことを前提としているからだ。
「謝れば許される」という傲慢
「謝罪の儀式」に慣れた人は、謝罪する意味を理解していない。
謝罪をすればその事柄は許されるという認識がある。
極めて個人的な関係だからこそ「形だけの謝罪」は成立しないのに、逆に、極めて個人的な関係だからこそ「形だけの謝罪」で済むはずだと誤認する。
この逆転した認識は、どこから来るのか。
それは、「親密さ」を「甘えの許容」と取り違えているからだ。
第三者による暴力――「男が謝ってるんだから」
夫婦間や恋人間で男性が謝罪をしたときに、それを許容しない女性を「わがまま」とする第三者がいる。
「彼は謝ってるんだから、許してあげなよ」
「いつまで怒ってるの?」
「そんなに根に持つなんて、器が小さい」
こうした言葉は、被害者である女性に向けられる。
しかし、本来、謝罪とは極めて個人的かつ限定的なものであり、謝る側が許しを前提とすることは傲慢以外の何物でもない。
許すか許さないかは、被害者の絶対不可侵の権利である。
第三者がその権利に介入すること自体が、暴力である。
そして、謝罪の儀式の成立を拒むことは、本来、関係性への誠実さの表れでもある。
「形だけの謝罪では済まない」という態度は、関係を大切にしているからこそ取られる態度なのだ。
平行線の認識と強制される歩み寄り
「謝罪の儀式」における、被害者と加害者の認識は平行線である。
第三者に「許せ」と圧力をかけられる
この平行線の認識に対して、歩み寄りは常に被害者に求められ、強いられる。
加害者は「謝った」という事実だけで免罪され、被害者は「許さない」という選択を責められる。
この同調圧力は、被害者の傷つきをコミュニティ全体で矮小化し否認するという不正義だ。
そして、このシステムが支持されるのは、不健全に公平を求める社会病理である。
「愛しているなら許すはず」という幻想
親密な関係における謝罪の不誠実は、なぜ生じるのか。
突き詰めるなら、謝罪という行為を根本的に不本意な事柄としてしか捉えておらず、親密さによって、それを行わなくてもいい環境として機能すべきだという幻想を抱くからではないだろうか。
その心理構造は、こうだ:
「自分のことを愛しているなら、自分の罪を見逃してほしい」
「愛しているなら、自分の不誠実など気にしないはずだ」
「何でもない相手さえ、謝罪の儀式で自分を許してきたのだから、
自分を愛している人であれば、謝罪の儀式は当然に成立するはずだ」
とんだ「甘え」である。
最も誠実に対応すべき相手にさえ、自身の不誠実の受容を求める。
これは関係性の構築における基本を会得できずにいるからに外ならない。
そして、その不誠実を強いることを正当だと誤認する学びは、幼少期から繰り返される「謝罪の儀式」にあるのではないか。
逆転した「親密さ」の認識
「謝罪の儀式」に慣れた人にとって、親密さとは何か。
それは「自分の不誠実が許される関係」である。
しかし、本来の親密さとは、互いが誠実であることで初めて成立する関係である。
この認識の逆転は、深刻な問題を生む。
この二つの認識は、まったく異なる。
そして「謝罪の儀式」に慣れた人は、前者の認識しか持っていない。
関係性の破壊―「謝ったのに」という恨み
形だけの謝罪を拒否された加害者は、しばしば被害者を恨む。
「謝ったのに許してくれない」
「いつまで怒っているんだ」
「俺はこんなに謝っているのに」
この「恨み」こそが、「謝罪の儀式」の本質を暴いている。
つまり、謝罪は相手のためではなく、自分のためなのだ。
謝罪することで自分が免罪されること、それが目的である。
相手の傷が癒えることは、二の次である。そ
して、その免罪が得られないとき、相手を責める。
これは、謝罪ではない。これは、暴力の継続である。
DV・モラハラとの構造的類似性
この構造は、DV(ドメスティック・バイオレンス)やモラルハラスメントの加害者の行動パターンと酷似している。
典型的なDV・モラハラのサイクル:
- 暴力・暴言を振るう
- 「ごめん」と謝る(泣いたり、土下座したりすることも)
- 優しくなる(ハネムーン期)
- また暴力を振るう
このサイクルにおいて、「謝罪」は暴力の一部である。
謝罪は、被害者を関係に引き留めるための道具として機能する。
そして被害者が許さないと、「謝ったのに」という新たな暴力が始まる。
「謝罪の儀式」は、このDV・モラハラの構造と同型である。
幼少期から「謝罪の儀式」を内面化した人は、親密な関係において、知らず知らずのうちにこの暴力的構造を再生産する。
社会病理としての「謝罪の儀式」
日本におけるこの社会病理は、様々なところで障害として立ちはだかり、問題を改善させないために役立っている。
すべてに共通するのは、「謝罪」という形式が、正義の回復を妨げる装置として機能しているということだ。
個人的関係から社会構造へ
最も親密な関係における「謝罪の儀式」の問題は、個人の問題ではない。
それは、幼少期から社会全体で刷り込まれた構造の問題である。
保育園で「ごめんね」「いいよ」を強制された子どもが、
大人になって恋人に「謝ったのに」と言う。
第三者に「謝罪の儀式」を強制された子どもが、
大人になって友人に「もう許してあげなよ」と言う。
個人の関係性の問題は、社会構造の縮図である。
だからこそ、この問題を変えるには、個人の努力だけでは足りない。
社会全体で「謝罪とは何か」「許しとは何か」「正義とは何か」を問い直す必要がある。
親密な関係における「謝罪の儀式」の破壊力は、その問いの緊急性を示している。
14. 代替案:真の謝罪とは何か
では、真の謝罪とは何か。心的外傷研究や修復的司法の観点からは、以下の要素が必要である:
- 真実の確認
「何が起きたのか」「誰が何をしたのか」
「どのような損害が生じたのか」 - 責任の明確化
「誰に責任があるのか」「なぜそれが起きたのか」
「何が問題だったのか」 - 正義の回復
「被害者の名誉の回復」「加害者の責任の引き受け」
「社会的な承認」 - 修復への道
「具体的な償いの提示」「再発防止の約束」
「時間をかけた関係性の再構築」
これらがあって初めて、真の修復が可能になる。
「ごめんね」という文言だけでは、何も始まらない。
15. おわりに:変革の可能性
日本社会に深く根付いた「謝罪の儀式」は、個人の問題ではなく、構造的な問題である。
幼少期から繰り返し経験し、内面化され、社会全体で再生産されてきた。
しかし、構造である以上、変革の可能性もある。
変革は可能だ。しかし、それは容易ではない。
「謝罪の儀式」は日本社会の深部に根ざしている。それを変えることは、社会の在り方そのものを問い直すことになる。
しかし、だからこそ、問い直す価値がある。
真実と正義のない社会で、誰が幸せになれるだろうか。
表面的な「和」のために、どれだけの人が傷つきを押し殺しているだろうか。
本当の意味での「和」は、正義の上にしか築けない。
ハーマンが示したように、修復への道は真実と正義から始まる。
日本社会もまた、真実と正義に向き合うことから始めなければならない。
あなたも「ごめんね」「いいよ」を強制された経験はありませんか?
あなたの傷つきは、本当に「迷惑」程度のものでしたか?
この論考が、同じような経験をした誰かの言葉になれば幸いです。
2025年11月5日 (水) Copyright © ハココ@WLTOS
無断転載・複製禁止、
出典を明記した上での引用のみ許可します。

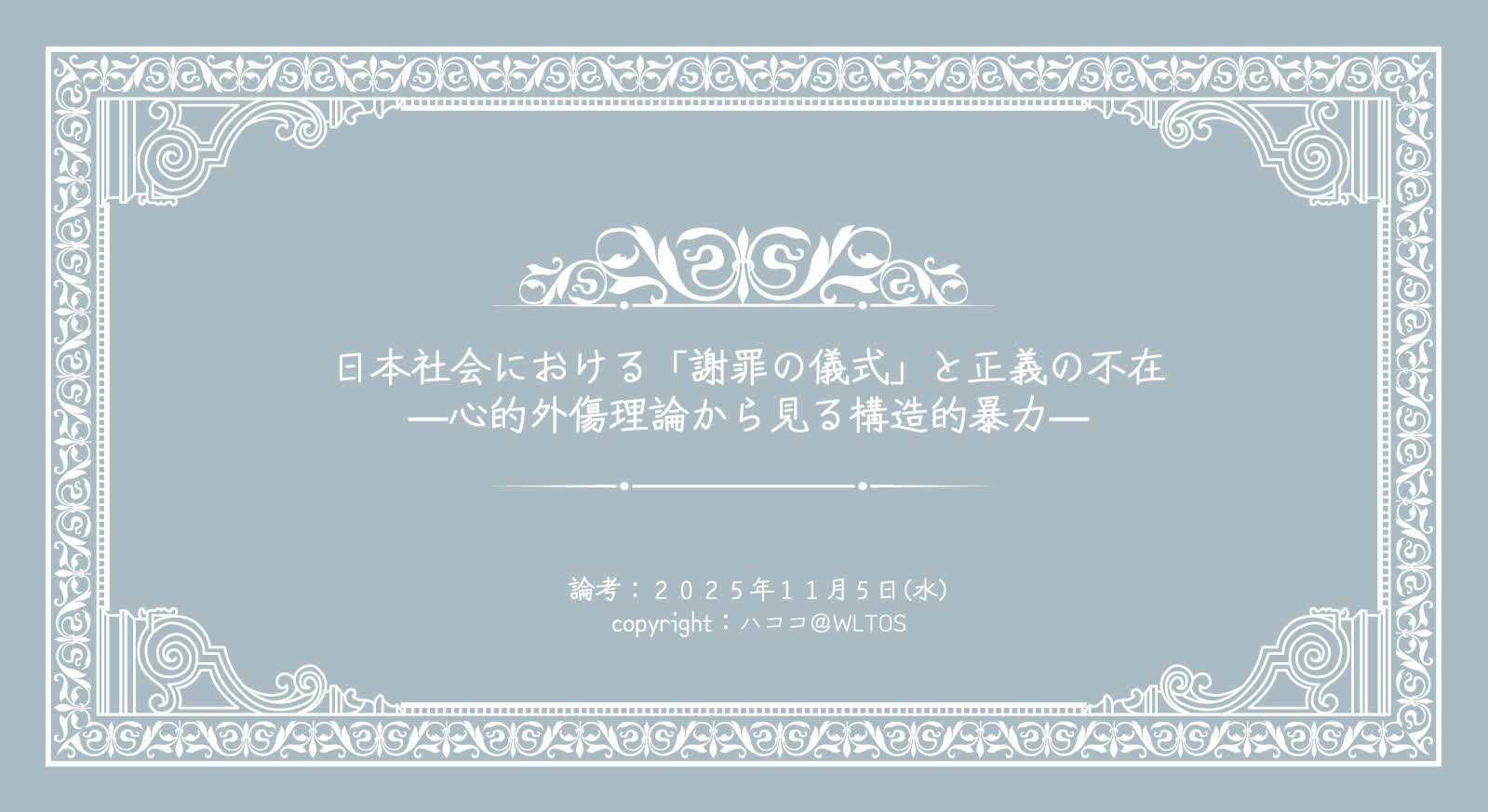


コメント