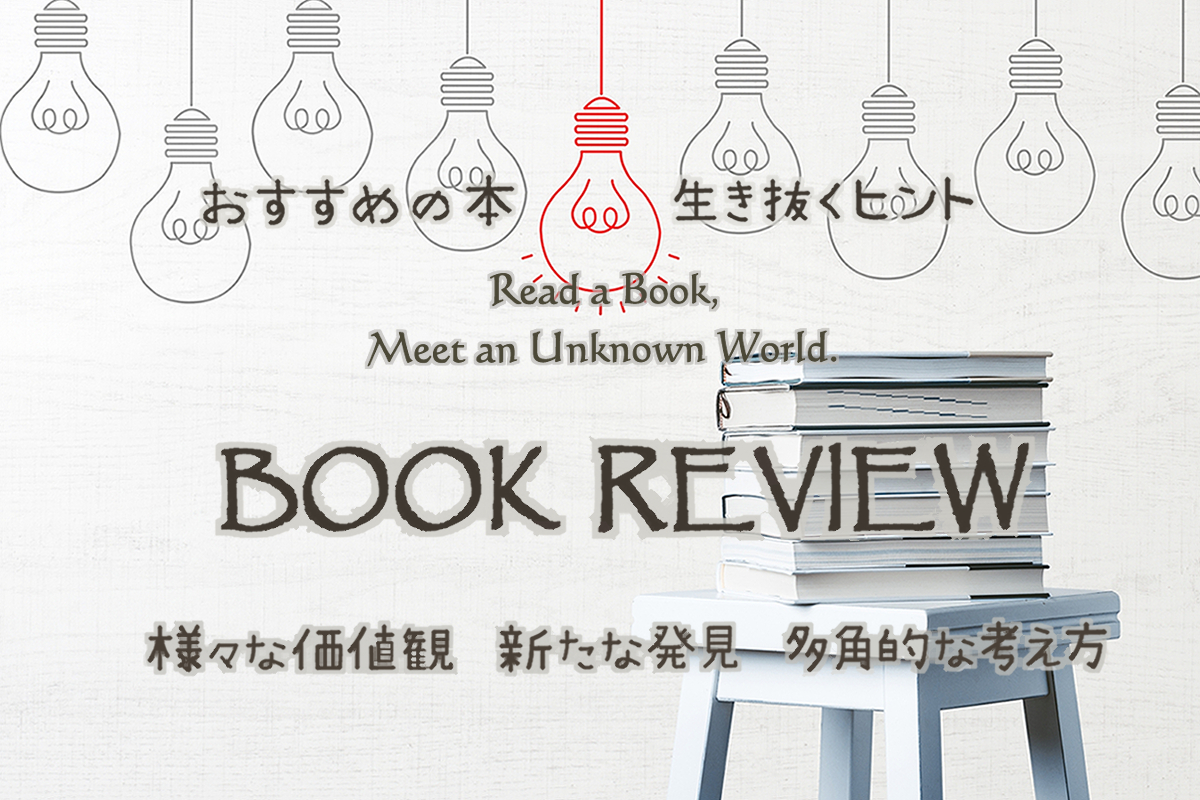「夜と霧」 著・ヴィクトール・E・フランクル
ー
おすすめの本、第一号は、このブログを作ろうと思ったきっかけである、この本。
『夜と霧』は言わずと知れた有名な本(だと思っているのだけれど)。名前は聞いたことあるけど、読んだことないな、というひともたくさんいるだろう。
内容は、第二次世界大戦時のナチスによる強制収容所(ホロコースト)で体験したことを記し、それらを心理学的に解き明かすことを目的とした本だ。
極限状態の人間の心理変化が手に取るようにわかる。わたしが読んだものは新装版で、若干、やわらかい言葉遣いに直されているものなのではないか?と思っているのだけれど。
わたしが経験したことをもとに考えていたこと、人間の心理、そういう場面に遭遇したら、それが常態化したらどうなっていくのか。考えていたことが正解に近いと知いように思えて、なんだかうれしかった。空想と現実が混ざっていたわたしの考えが、わたしが考えて辿り着いたものが、間違いではないと知ることができた。
こんなことを言っては、批判を受けるかもしれない。
わたしは彼らの経験は体験していないし、想像するにもあまりに難しく、その心理を解るなんて言ってはいけないことだ。その場にいた者たちとしか分かち合えないだろうこと。
それらを、心理学として昇華してみせた、その強さ、使命感、それは著者であるフランクル氏自身のその先の人生を生きる指針にもなっただろうことで。
けれど、たとえばなのだけれど、収容所に行かなくても似た心理を味わうことはある。
同じような考えに辿り着くことはある。
そこに至る経緯によって、受け取る側の重さも、語る側の強さも、変わるだろうことで、きっとわたしなんかの経験からの答えとやらとは、やはりなにか違うのだろうけれど、それでも、彼が考えた生きる意味と、わたしが考えた生きる意味が似ていたことに、よろこびを覚えた。
絶望の果てに見るものとは。ひとが生きる上で最も大切なものとは。生きる意味とは。
精神の自由は誰にも奪えない。
心、その魂は自分だけのもの。
苦悩にさえ意味を見出せる。
殺すものも殺されるものも人間であり、人間はどちらにもなり得る。
自分というもの、名前や肩書きで表す己などではなく、その者の持つ、誰も汚すことのできない、魂、精神こそが自分であるということ。
戦争下、強制収容所という場所、そこで起きたことは、筆舌し難き光景であり、身をもってそれを感じつくし、そうして夢見ていた生還を果たしたとき。ようやくそれを感じたとき、今度はその現実が絶望的であることを知らされたりもする。
生還することを夢見ていたのに、生還したことを辛く思うこともあっただろう。
「夜と霧」の中に、PTSDに関する記述がないことをわたしは不思議に思った。
どうやら、その病名というか概念というかは、まだ作られていなかったらしい。
フランクル氏はもちろん、生還者たちはPTSDにあって当然ともいえる体験をした。
事実、フランクル氏は晩年まで悪夢を見ることがあったらしい。
幸福であることだけが生きる意味や価値ではない。
幸福であるにこしたことはないが、自分の精神的な部分を如何に、どのように高めることができたか、それこそが価値となる。
自らが何者であるかを問い続けることは、何者でもない自分にすらも価値を見出せるのだ。
宗教的なこともあり、神の存在、祈ることについてなど、フランクル氏を支えたのものに信仰があったことは否めない。しかし、信仰とは愛にも置き換えられるだろう。生死も分からぬ妻の確かな存在に支えられていたフランクル氏。
日本人には馴染みのないひとも多い、信仰。それは心から愛するその相手を想うことと似ていた。
心理学として
わたしは、体験記としてではなく、心理学の本として読んだ。
「感銘を受けた」というネットの感想には、戦争の残酷さを知ることができた、生きる指針になる一冊、などとあったが、中には、気分が悪くなり最後まで読めなかった、というものもあった。
文字だけだありながら、ありありと想像したその想像力は素晴らしいものだけれど、なんだか悲しかった。それを実際に経験したひとたちは本を閉じることはできないし、やめることもできずにそこにいて、見ないことにすることは死であった。死を選ばずにいたら、感情を封じ、感じることをやめることにしたって、なくなることのない現実で在り続けて、逃げられもしなかったのに、現代のわたしたちは、容易く目をそらせるし、簡単になかったことにできる。
これらはなんにだって言えること。戦争だとか強制収容だとかでなくても、そこらに溢れている。
いじめ。差別。犯罪。事故。事件。毎日たくさん起きて、報じられても、誰にも知られることがなくても、いつの間にどこかへ消えて行く。
けれどそれらすべてに当事者がいて、そのひとたちの中で、それが終わることや、どこかに消えて行くことなんて絶対にない。
そのひとたちが、自身に起きたことをについてどう考えるのか。それらの一種の手本というか、参考になるだろう事柄として、「夜と霧」は素晴らしいものだった。
ただ、そんな現実を生き抜く事ができたなら、きっと、読まずとも辿り着けるものであるとも感じた。
ひとが絶望するのは、大きな事柄でだけではない。客観的な大事件だけではない。そして追い詰めるのは悪人ばかりでもない。
そのときに皆が考える。自分はどうして生きるのだろう。けれど、フランクル氏の答えだけがすべてではない。一例であると考える。自分なりの答えを見つけられてこそ、ひとは生きていくのだろう。たとえ、文にしたら同じでも、そこに至る思いや、思考の辿った道、その意味は皆全く違う。
そしてさらに思うこと
これはキリがない話になのだけれど。
「夜と霧」は人間というものは特別である、という感じ強かった。人間の心理学なのだから仕方ないとは思う。
ただ、生きているのは、死を体験するのは、感情があるのは、思考するのは、人間だけに与えられた特権であるかのような印象に少し戸惑いを覚える。
人間は、極論たくさんの死体にまみれて生きている。木造住宅は木の死体、樹木の死体である机の上に死にゆく花が飾られて、植物の死体である綿の服を着たり、バッグや靴には死んだ動物の皮を使ったり、食事は家畜の死体と植物の死体を調理したものなのだ。
人間はたくさんの死を消費して(浪費すらして)生きているのだ。
命をいただかない、菜食主義。なぜ、植物の命は気にしないのか。
とにかく人間は傲慢なのだ。自分の都合で生きるものを差別する。自分で動くものは命としての価値が高く、動物の中でも特に猫や犬の権利はすさまじい。逆に鳴くことをしない(と人間が判断した)もの、自ら動かない(と人間が判断した)ものは、生物とは呼ばれているのに、死んだとは表さないし、それらの命を刈り取ることには抵抗なんてのもはなくて当たり前なのだ。
人間の都合である。死体に囲まれているなんて、気持ち悪い。植物が枯れることを死なんて大層な言葉で表す必要もないし、そんな表現をしていたら、不都合でしかない。
自然界に魂はないのか。彼らに意思はないのか。誰もないとは断定できない。だって解りようがないから。けれど、あったら邪魔だから考えない。
けれど、それこそ「夜と霧」にある、生き残るためにすること、図々しくなることや、無頓着になること、慣れること。人間は高い知能で生き物を生き物と認識し、食事にも、衣にも住にも遊にも、消費される生き物の死に無頓着になれる。自分が生きるために。それが人間や生き物のあるべき姿だとばかりに。
けれど、たまに考える。自然界の住人たちのこと。彼らはなにを考えて生きているだろう。何を思って生きているだろう。なにをどう感じるのだろう。わたしたちが消費する死に思いを馳せる。
それでも、わたしは生きるために今日もたくさんの死を消費することに変わりはない。