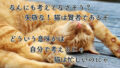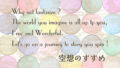子供は親に無償の愛を捧げざるを得ない
ー
よく、親というものは、子供への無償の愛を与える、とかいう、ふわっとした素敵美し性善説の神話が語られたりしてますよね。
でも。
親だってそんな聖人君主じゃない!
普通にイライラするし嫌なことは嫌なの!
ただの人間なんだから!
という反論がいい感じに浸透してまいりました。
そうです。親は無償の愛情なんてものを標準装備などしていません。
しかし、無条件に信頼して、愛情をくれる存在がいます。というかそうせざるを得ない存在。
親がただの人間であるためにイライラしてしまうという、その子供です。
どんなに酷い扱いをしても
子供は生まれてくる家庭を選べません。親を選んだりなんて、できない。
けれど、幸福なひとたちは高らかに、赤ちゃんはママ(あなた)を選んで生まれてきたのよ。という呪いの言葉をかけます。
酷い扱いを受けることろにあなた(子供)が望んで生まれてきたのだなんて、どんな陰湿な嫌がらせかと。
子供というものは、生まれてから長いあいだ、親を神様として生きていきます。
親が教えてくれたことを学び、親の価値観を受け継ぎ、親に従い、親を受け入れ、生きて行くことしかできない。親が与えてくれるものしかないのです。
それがどんなに間違っていても、世間とどんなにかけ離れた考え方をしていても、それが当然であるとして受け入れるしかない。
殴りつけられるのが当然であったら、それを受けます。
罵られるのが当然であれば、それも受けます。
無視されるのが当然なら、それを受けています。
それを受け入れることが当然と教わっているからです。そして、それは普通ではないのだと、助けに来るひともいないので、痛くても怖くても受け入れるしかない。
助けを求めることを教わっていないので、助けてくれる人がいることも知らない。それすらも普通なんだと思ってしまう。そういうものである、と親が教え込んだから。
もしかして、これは普通ではないのだろうか?と疑ったとしても、親のことを悪人とするのは嫌だなと、どこかで思ったりします。それに、助けてなんて言ったら、もっと酷いことになることが起きたりもします。
感情も感覚もないことにしてまで、親の暴力を受け入れ続けるしかありません。
どんどん壊れていく自分、消えてしまいたい……。
それでも子供だから、親の行為を受け入れ続けるしかない。受け入れたくなんかない。でも、ここに居るしかない。
それが地獄以外の何ものでもなくても、そこにいるしかない。
受け入れ続けることが愛、だなんて言ったら、語弊はありまくりです。
でも、そうすることが親から求められていて、そうするしかないからそうしている歪んだ親子関係。
愛と憎しみは表裏一体。親に酷い扱いをされると知らなかった頃、無条件にそのひとが自分の保護者としてしまいますし、そうするしかありませんよね? その保護者に育ててもらって生きなきゃならないと自覚してしまう。
その自覚は、一般的な家庭の範疇にいれば、問題もなく良いものとなるでしょう。人間としての当然に備わっているものなのかもしれません。
それを、裏切られてもいたと気づいても、子供が自力で出て行くなんて出来るわけもなく、出ていけたとしても、世間が受け入れない。子供は親のもとにいるのが幸せである、というのが常識であるから。
そして、酷いことをしても子供が従っていることに甘える親のもとに居続けなければならなくなる。
「子どもの権利条約」に定められている権利
基本的な考え方の4つの原則
4つの原則は、「こども基本法」(2023年4月施行)にも取り入れられています。
差別の禁止(差別のないこと)
すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障害、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障される。
子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)
子どもに関することが決められ、行われる時は、「その子どもにとって最も良いことは何か」を第一に考える。
生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)
すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障される。
子どもの意見の尊重(意見を表明し参加できること)
子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮しる。
子どもの権利条約は前文と54条からなり、1~40条に、生きる権利や成長する権利、暴力から守られる権利、教育を受ける権利、遊ぶ権利、参加する権利など、世界のどこで生まれても子どもたちがもっている、様々な権利が定められています。また、難民や少数民族の子ども、障がいのある子どもなど、特に配慮が必要な子どもの権利についても書かれています。
条約に定められている権利には、大きく分けると以下のようなものがあります。
生きる権利
住む場所や食べ物があり、医療を受けられるなどして、命が守られる
育つ権利
勉強したり遊んだりして、もって生まれた能力を十分に伸ばしながら成長できる
守られる権利
紛争に巻きこまれず、難民になったら保護され、暴力や搾取、有害な労働などから守られる
参加する権利
自由に意見を表したり、団体を作ったりできる
条約に書かれている子どもの権利を守るために国が法律を整え政策を実施すること、また、子どもの権利が実現するようにする責任はまず親(保護者)にあることなども定められています。
子供の権利は、いまどこに?
現在クローズアップされている宗教における二世の宗教の自由の問題。これも親が子供に甘えているという状況と似ています。
けれど、子供の権利を守ろう、に宗教が絡んで難しいものになっているのが現状です。宗教の自由だから口出しはできない。
それは、子供の権利が親の中に飲み込まれていて、子供の前に親の意見が通っているということ。
そんな状態で、子供の権利は守れるのでしょうか?
はっきり言って、子供の宗教の自由の権利はないも同然です。
親の信仰する神を子供も信仰しなければならない。親はその信仰が素晴らしいからと子供にも信仰させたい、は当然なのかもしれません。そこにもし、宗教の教えが子供の幸せも親の幸せもそこに在るという言い方をしたら、尚のことそうさせたい。
自分の正しいを子供にも教えたい。理解はできますが、それはどうにも、加害的になってしまう。
ちなみに、これはカルト的な宗教だけで発生するものではありません。古来からある宗教でも起きることです。
子供は、その親から生まれてしまったがゆえに、その親に甘えられてしまいます。逆転した関係です。親が子供に甘えるという状態、関係の逆転は、家族と言う檻であると感じます。
ヤングケアラー。きょうだい児
それらの根本は、「家族のことは家族で」という日本の通念。他人はお節介を働くべからずの精神。
地域包括の支援、地域で支援して障害者も安心して暮らせるように。という、なんとも美しい精神を実行させようという感じに進んでいますが、地域で見られないから施設があって、それで何とか生活していたのに、正しい知識さえあれば大丈夫、みんなで支えましょうね。と家庭に戻そうという政策です。
どうにも解せません。
ヤングケアラーは若者だけの問題ではなく、ヤングケアラーであるがためにたくさんのことを諦めていきてきて、大人になってもそのままケア要因としての人生のまま。ヤングケアラーでもあるきょうだい児は家族だからと、たくさんのこと我慢して育ち、親亡き後、将来はそのきょうだいを押しつけられるのです。それが当然だと周囲も思っている。
家族のことは家族が責任を持つ、というのが美徳。
家族の面倒を見ないのは人でなし。家族なんだから、と支援員すら子供をケア要因として数えるのが当然であるという社会。
子供たちは、ツライ、嫌だ、なんて言えず、ひたすら我慢し続けます。
親の責任? 自己責任?
ときに、障害を持った子供が第一子だったことで、ケア要因としての第二子をもうける親がいます。
きょうだい児の当事者も、反対の順番でうまれたならまだ納得できるけれど、ケア要因にするために作られた自分と言う存在に、どうにもないやるせなさを覚える、親の精神を疑う、と言った、親の子供の権利や人生に対する軽視を指摘します。たとえ反対であったとしても、将来にわたりずっと弟、妹の世話を続けて当然だなんておかしいと。
親がケア要因としての子供を作ることは、きょうだいがいれば面倒を見てくれるはず、だって家族なんだから、という甘えと、まだ見ぬ我が子に頼らざるを得ないほどの過酷な現実があるのでしょう。
親が子供に甘えるのが前提と言うのは既におかしな状態です。が、そうするのが正しいと思っているのは、家族くらいしかこの子供を見てはくれないと理解しているからこそで、つまりは社会が面倒を見てはくれない状態だから。
とはいっても、そのために生まれてきて、そうすることがあなたの人生だと言われる子供の気持ちは、もう一人のわが子のための、自分とは?
そもそものところで、人生がはじまった時点で、もうおかしな状態にいるのです。
文句は親に言え。と言われても、親に文句を言うことが無駄であること。社会を恨んでも仕方ないと言ったって、そもそもの原因は社会であるのは確かです。
貧困の連鎖
親が貧困であれば、子供はその中でしか暮らせません。受けられる教育の質も、所得と共に落ちていきます。親自身が学習の支援をする余裕もなく、学校と言う集団にもなじめず。生活の苦しさから、高校進学すら平然と否定する親。その背景には自分もそうであるけれど、何とかなっている、というよくわからない根拠があったり、とにかく生活費を稼ぐ要因になってほしいだとか、これも親が子供に甘えている状態で、社会もそうさせる。
そして、自己責任。という言葉が子供も親も追い詰めていく。
高校進学して、大学にも進学。となれば、奨学金が便利だよ、進学はあきらめなくていいんだよ、と制度もよく知らせずに、生まれて二十年経ってもいない高校生に、自己破産レベルの借金を背負わすことを教師が進めます。
仕送りもなく、とにかく生活をしようと、女子学生は仕方なくやりたくもない性産業に足を踏み入れることもある。極端な話ではありません。
けれど、楽しい夢のキャンパスライフを過ごし、苦労するのは良い事と考えるような中高年の男性が、なんでこんなことをしているんだ? 努力が足りない。頭が悪い。などと言いながら、女の子を買っていくんです。
俺はなあ、と現代では通じないイージーモードだった頃のハードモードを生き抜いたことを誇らしげに語り説教し、色んな意味で楽しいでしょうね。
スーパーハードモードを生きる現代の学生を知らないという情報に疎いヒトたちです。
闇バイトに足を踏み入れるのも、それなりに苦悩があっただろうこと。辛すぎる現状で、生活もままならないのに、一生懸命頑張っても報われない生活。そこにラクして稼げるものがあるなら飛びつきたい気持ち、わかります。
現代にそぐわない、イージーモードの頃のハードモードの打開策を語る人々しかいないのに、それを例にして説教されるのは、スーパーハードモードを生きる彼らにとって、憎しみすら湧くことでしょう。
子供は親を選べない
子供は親を選べません。なのに、その親を親とするしかない状況を受け入れてくれる。受け入れ難くとも、受け入れるしかない。
産みたくなかった!だの、産まなきゃよかった!だの、自分を勝手に作った親に言われるのはあまりにおかしな状況。頼んでない!と言いたいのは当然です。
生まれてこなければよかった、を子供には言う権利があると思いますが、産まなきゃよかった、を言う権利は親には無いに等しいです。無いとするのが望ましいし、無いと言い切りたい。
望まぬ妊娠、その混乱、性被害によるもの、そこまで含めると、難しい問題ですが、性行為に同意していたならその結果なのだから、産まなければよかった、などという権利はないでしょう。
それでも、子供は無条件に親にします。その子の親とします。
でも、そのヒトが親であることを否定することはあるでしょうし、違うひとを親にする権利はその子供にあると思います。
それでも、ひとまず、親として認めることになってしまう。そのヒトから生まれたから。
けれど、その親が、自分の責任のない行為によって子供を作ったのだから、親であるから、子供が育つにふさわしい環境に子供を置くのが親の責任。
子供のために親である権利を誰かに剥奪されるとき、それは親が子供に甘えていて、立場の逆転が起きているからでしかなく、養育と言う状態ではないから。
でも、それでも、児童福祉もなかなか踏み込めず、消えてしまう子供たちが存在します。
子供の権利は、いまどこにあるのでしょう?
子供たち、よく頑張ったね
本来なら、そんな台詞が必要ないことが望ましい。
助けなければならない子供なんていなければいい。
でも、現代の社会では、まだ子供の権利は親の権利の中に飲み込まれているから、外側にいるひとたちが、親の反対を押し切って子供だけを優先させることがなかなかできない。
そんな親の元で過酷な環境を生き抜いたサバイバーたちに差しのべられる支援の少なさ。かつての子供たち。よくここまで生き抜いたね。そうやって、せめて助けられたときに受け入れる体制だけでも、長い支援ができるように、社会で問題を話し合わなければなりません。
生き抜いたことを後悔させる社会であっていいはずがない。
たとえ、その子供のこと自体を思えないなら、知らない子供のことなんてどうでもいいなどというなら、この提案と言うか、とても当たり前な事実をここに記します。
現在の子供の問題は、まわりまわって今の大人の老後に直結しています。子供たちのためにすることが、自分に良い結果として返ってくるのです。年金、社会福祉、そういったものの財源は、今の子供たちが大人になって、社会で働くことで得られるのです。
自分には子供はいない、と子育てに関することに全く関心が無いというひとたち、ちょっと待ってください。考えてもみてください。
あなたは、その自分の子でもない子たちに将来支えてもらうのですよ? 介護してもらうかもしれないし、迷惑をかけるつもりはなくても、絶対になにかしらお世話になります。
その子からこういわれたら、どう思いますか?
自分の親でもないのに、なんで私らの稼ぎの税金を勝手に使われるの?
何もしてくれなかった大人をなぜ自分が支えなければならない?
全く同じ言い分ですよね?
年金だとか、社会福祉、それを当然の権利としたいなら、他人の子供にも関心を持つべき、という提案です。