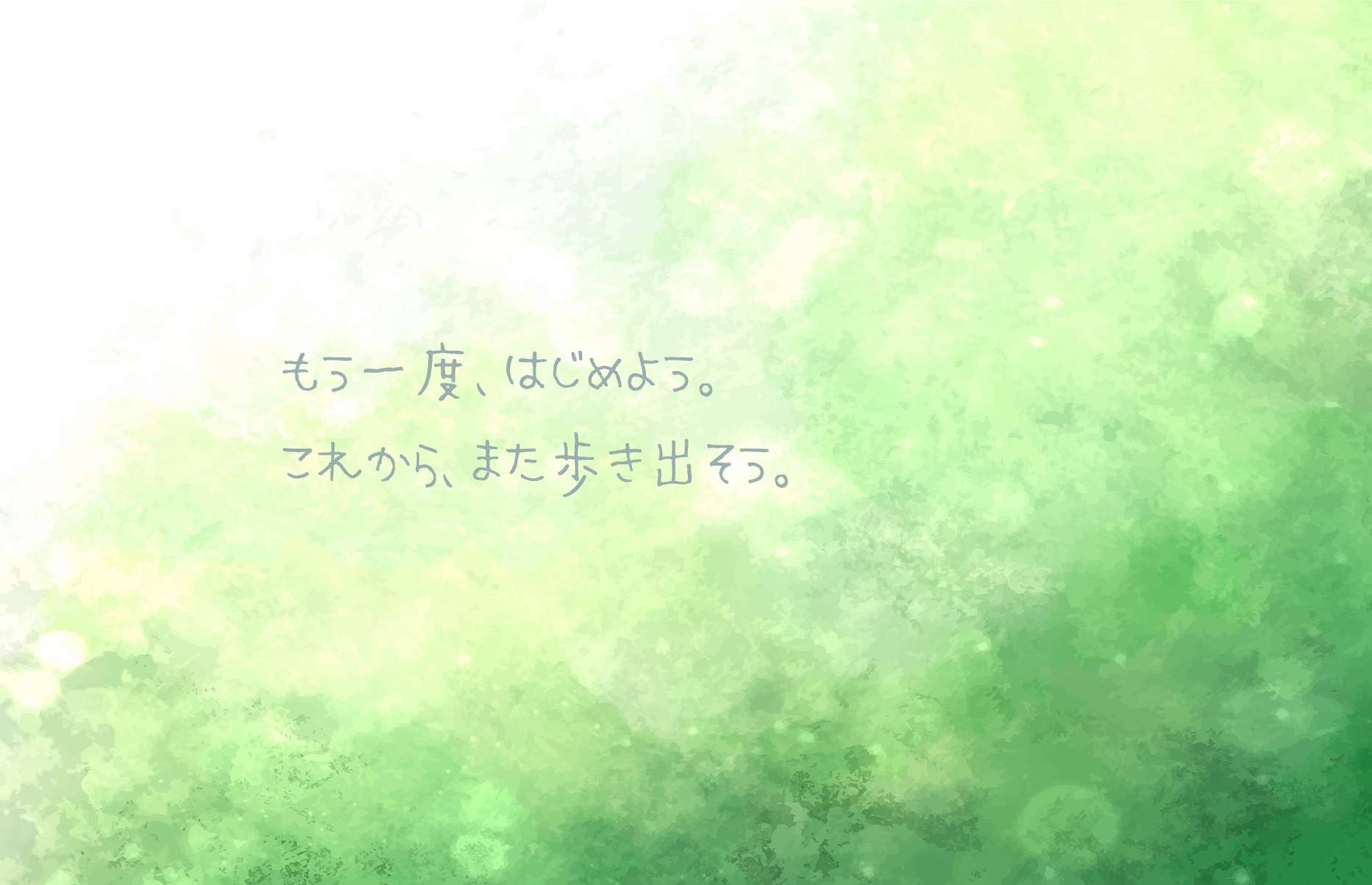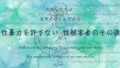支援が無かった4ヶ月
―“生きている”ことが精一杯だった
ー
この記事で明らかになること :
✓ 障害支援区分4の独居者が4ヶ月間放置された経緯
✓ 福祉課長の「法的措置を取れば」発言の衝撃
✓ 「支援しやすい人」から助かる構造的問題
✓ PTSD/DIDが障害年金対象外である矛盾
なぜこれを書くのか :
同じ状況にいる人、これから陥るかもしれない人のために
行政・支援者に現実を知ってもらうために
社会の構造的問題を可視化するために
わたしは、2024年の年末から約4ヶ月間、行政からの支援が事実上止まった状態にありました。
生活保護で障害支援区分4の判定を受けていたはずのわたしが、どうして支援のない日々を過ごすことになったのか。
その話をしようと思います。
でもこれは、“特別な誰か”の話ではありません。
わたしのような人は、きっとあなたの隣にもいるはずです。
もしかすると、あなた自身がそうかもしれません。
障害支援区分4で4ヶ月間支援が途絶えた経緯
なぜブログが止まっていたのか―支援が完全に途絶えていた
はじまりは、ヘルパーの仕事に疑問を呈したことでした。
「可燃ごみに不燃ごみを混ぜても見えないようにすれば平気」
ヘルパーはそう言いました。それに食器洗いを頼んだら、かなりの水量で出しっぱなしで、その上にあとで確認したら汚れは落ちていなかった。
たった2日の利用で気になる点、言動が多くて、相談支援員(ヘルパー事業所の責任者も兼ねている)に申し入れました。ゴミや水道の使い方については改善すべきと認めてもらえたのですが、それよりも驚くべきことを聞くことになりました。
わたしは常に玄関のカギを開けて対応できるほどの健康がありません。寝込んでいることもしばしば。そのため、事業所にアパートの鍵を預けていました。その鍵が「ヘルパーの個人管理」だと告げられたのです。待ってください!聞いてないです!わたしは抗議しました。
ところが、相談支援員から返って来たのは「そういうふうに気になっちゃうなら、ヘルパー利用はやめたほうがいいんじゃないかなあ」という福祉や支援というものの根幹を覆すようなものでした。あまりのことに絶句です。
としあえず、後日、話し合いをすることになりました。
しかし、わたしはその後、高熱を出し、インフルエンザと診断され、相談支援員からも福祉課からも一切の連絡も無いまま、体力が回復し、自分から連絡できるようになるまでの約一ヶ月を福祉の支援が皆無で過ごすことになりました。
一ヶ月経って福祉課の窓口に「話し合いの件はどうなっているの? どうしてわたしは放置されているの?」と聞きました。返って来たのは「あなたから何の連絡もないから何も進められなかった」という言葉でした。
ヘルパー事業所との契約解除の不当性
その後、話し合いの場は作られました。しかし、1ヶ月、生き延びることだけに必死になっていたわたしは怒りを抑えられませんでした。激昂に近い態度かもしれません。でも、わたしが言ったことは正当なことのみで、同席した福祉課の人も、怒っているのは怖かったけど、正しいことしか言っていないと言ってくれました。
相談支援員は「もう信頼が崩れているのは明らか。でも次が見つかるまで責任を持つ」そう言い残してその場をあとにしました。
しかし、その後、わたしへの支援は再開されることがありませんでした。
わたしへの答えは、契約解除でした。
解除理由は
「通常の範囲を越えた過剰なサービスを不当に執拗に求めた」
「謝罪も改善案も受け入れてもらえなかった」
「精神威圧的な態度で該当職員は心身ともにダウンした」
「職員を守れない」です。
(ちなみに、この書類はダウンしているという該当職員の名前で送られてきました。また、該当職員はこの事業所で唯一の相談支援員で、受け持っている人も多くいるのに、福祉課でこの職員がダウンしたことによる弊害はまったく聞かれないそうです。不思議です。)
なお、改善案とやらは一切提示されていません。それに謝罪は必ずしも受け入れなければならないものでもありません。
そもそも「通常の範囲を越えた過剰なサービス」とは何をさしているのか。
わたしはこれを「不当な契約解除だ」と福祉課と県の福祉事務所に申し入れました。しかし「契約の問題は二者間で解決すべし」とい県の見解があり、市の福祉課も何もしてくれないという状況にあります。
(でも、まだあきらめていません! 不名誉を退けて、わたしから契約解除をしたという状態にしたい)
そもそも、この相談支援員にはいろいろとおかしな部分があります。
存在しない「以前から担当している解離性同一性障害の女性」の話をわたしにしていました。(契約解除後に存在しないことを福祉課の人に確認して知りました。)
わたしに希死念慮が常にあることを知りながら、その話題のときに「自分の父親の自殺の詳細」を話してきた。
わたしの中学からの同級生(親友)の兄の話(元利用者)をしてきたため、兄との関係で悩んでいる親友を思い、わたしは板挟みになった。
支援計画書に署名を求めたとき、名前や住所欄以外がわたしのものではなかった。作り直したそれに署名はしたが、結局わたしの支援計画書をわたしは受け取っていない。
――えっと、守秘義務はどこに?
福祉課の対応と課長の発言
福祉課での出来事―障害支援区分4、独居でありながら放置
問題のある相談支援員にあたってしまったという不運だとして、わたしはそれを避けることもできなかった。なぜなら、わたしの地元の福祉課ではそこがどんな事業所なのか聞く事ができないのだ。(できる地域もあるとのこと。)事業所の名前と連絡先が書かれた紙を渡されて自分で選んで決めることになる。でも口コミもなく、どこがいいのかさっぱり分からない。運が悪かった、というにはあまりに代償が大きかった。
そもそも、わたしは精神障害だけで障害支援区分4というそれなりに珍しい状態だ。そして支援区分4は独居では生活は無理、生存も難しいのではないか?という状態。それは、契約解除を通知してきた相談支援員が話し合いの場で言った言葉だ。そんな状態のわたしに4か月福祉の支援が途絶えたというのは、なかなかの状況のはずだ。
福祉課の人は契約解除と聞いて驚いていた。そしてとにかくはやく次を見つけなければならないから、今回は自分たちも一緒に探すといった。福祉課と連絡と取り合いながらわたしも探した。福祉課からは見つからないという返事が返ってくる。しかし、わたしの方では見つかった。「相談支援業務だけなら」という形ではあったが、有難い申し出だった。
しかし、ヘルパー事業所が見つからないことには何の支援もはじまらない。
わたしは支援がはじまるまでの代替措置を求めた。
社会福祉課課長の「人がいない」「法的措置を取れば?」という発言の衝撃
福祉には原則がある。
生存権を保証するというものだ。それが福祉の責務である。
しかし、事実上、わたしの生存権はまったく保証されていない。
その点を担当のケースワーカーに話しても「ごめんなさい」といわれるだけなので、社会福祉課の課長に問い質してみた。
すると、「原則はあるが、万能じゃない。リソースは限られている」と言われた。わたしは生存のために支援が必要だと話していた。それを退ける形である。
その上、「あなたがあんなに怒るからいけないんだ」とわたしの態度を責めた。わたしには怒る権利があるはずで、あれは正当な怒りであり主張だ。
それにわたしはトラウマの疾患で、理不尽に対する怒りは制御できない。だから「出来ないことを要求するのか?」と聞いた。すると今度は「あなたも今、私たちにできないことを要求している」と返した。
「障害によってできないこと」と、「福祉の責務を果たせないこと」を同列に語っていいはずがない。
でもきっと何を言っても通じないことを、この言葉で感じた。
「福祉の責務を果たさないというのは、職務放棄ではないか?法的措置も取れる状態ではないか?(しかしわたしにそれをするだけの体力はもうない。)」
「法的措置、取っていただけば良いんじゃないでしょうか?」
課長はそう開き直った。
本当に、わたしが困窮していることも、この人にとっては他人事でしかなく、生きるために必死にならなければならない、生きるために生存に必要なことを蔑ろにする必要がある状態を、この人は想像もできないだろう。
わたしが要求してはじめて「代替支援」が検討された。しかし、本当なら無料で受けられるはずのそれを、正式な形ではないからと自費で受けるというものが提案された。また、わたしには向かないショートステイだけしかなかった。
わたしはこの日から、一切、福祉課と連絡を取れなくなった。福祉課がトラウマ的な場所になってしまったのだ。
「支援しやすい人」から助かる福祉の構造
支援の優先順位と“コスパ”の罠―支援が届くのは“支援しやすい人”
「支援が必要です」と声を上げたとき、その声は“深刻な順”に届くわけではない。
現実には、“支援しやすい人”――つまり、言葉が明瞭で、感情が穏やかで、見た目にも「わかりやすく困っている」人のほうが、先に手を差し伸べられる。
この構造は、意図して作られたものではないのかもしれない。けれど結果として、苦しさが深く、表現が難しく、時に混乱してしまう人ほど、“後回し”にされてしまっている。
その“後回し”は、ときに命の問題にまでつながる。
だからわたしは、この構造に疑問を投げかけたい。
支援の優先順位と”コスパ”の問題
「支援のコスパ」という考え方
支援する人・団体の中には、こう口にする人もいる。
「この人は応援したら伸びそう」「支援しても変わらなそうだから、他の人にまわしたほうが……」と。
それはまるで、投資のように“リターン”を測って、支援の優先順位を決めているように感じる。
けれど、人の命や人生の尊厳を、“コスパ”で測っていいのだろうか?
支援の本質は、「どれだけ変われるか」ではなく、「いま、どれだけ困っているか」だと、わたしは思う。
それに、もっと大きな視点から“コスパ”を見れば、PTSDや解離性障害といった状態の、扱いにくい、支援しにくい人を支援しないことは、経済的な損失になる。そして適切に支援することが経済的利益になる。このことから他の先進国では、サバイバーへの支援が拡充されているのだ。
その他にも、本当の意味でのコスパで考えるなら、こうした存在に支援がないことで、いつしか拡大自殺や凶悪犯罪にまで発展することがあることを、社会は知っているはずだ。大規模な犯罪を起こした人は生い立ちに焦点が当たる。その生い立ちが壮絶であることにみなが驚く。でも、だからといって免罪されるわけではない。しかし、もし支援があったなら、その人は加害者にならず、被害者もうまれなかったことを、考えてみて欲しい。
この二つの視点こそが、社会福祉が考えるべき“コスパ”である。
PTSD・DIDが障害年金対象外という矛盾
心的外傷性疾患は障害年金の対象外?
わたしはDID(解離性同一性障害)とPTSD(心的外傷後ストレス障害)を持っている。
けれど、この2つは日本の障害年金の“認定基準”に含まれていない。
要するに、どれだけ生活に支障があっても、「制度上の対象外」だと言われてしまう。
これは国として、「この障害にはお金を出す価値がない」と言っているのと同じだ。
人としての存在そのものを、制度が“認めない”という拒絶を突きつけてくる。
他国では、どう扱われているのか?
たとえばアメリカでは、PTSDやDIDも精神障害の1つとして認定されており、支援や年金の対象になる。
イギリスやオーストラリア、カナダでも、トラウマに起因する精神疾患への理解と支援は日本より遥かに進んでいる。
もちろん、どの国にも課題はある。けれど少なくとも「制度上存在しないものにされる」ほどには、冷たくはない。
日本は、被害に遭った人間に対して「見なかったことにする」のがあまりに上手い。
それは加害者を守るためではなく、社会全体が「その苦しみを見たくない」と思っているからだと思う。
“支援しにくい人”こそ、支援が必要
感情の起伏が大きかったり、支援者とうまく信頼関係が築けなかったり、時には「わかってくれないなら、もういい」と諦めてしまう。
そんな「支援しにくい」人こそ、実は一番苦しんでいることが多い。
だから、わたしは伝え続ける。
あなたにとって“めんどう”に思える人も、生きるために必死で戦っている。
わかりやすさや“リターン”の有無だけで支援の優先順位を決める社会を、変えていかなくてはいけない。
障害支援区分4というわたしに支援がないままの状態でも、わたしより区分が軽い人たちには普通に十分な支援があった。この現実が、わたしにとってどれほどの悲しみであったのかを、このときに関わっていた誰が想像していただろう。
4ヶ月間をどう生き延びたか
支援がない国で、生きるということ―心身が削られていく
社会では「SOSを出そう」と叫ばれている。「助けて」と言えば応えると社会が言う。
しかし、現実は違う。
「SOSを出した人の中で、助けられる人の中で、助ける側の人が助けたいと思った人」が助かるのだ。先に言ったコスパ然り。支援者にとってメリットがあることが、助ける(助かる)基準だったりする。
わたしは明確に「助けてください」という文言を福祉課で何度も言った。助かるまでに4カ月がかかった。「助けてください」「今すぐ助けが必要です」に「ごめんなさい」と言われ続けた。「困っているのは分かっている。ものすごく大変なのもわかる。目に見えて痩せてきてもいて、心配です。でも制度がない。人でもない」これが現実の対応だった。
このままでは生きていけない。だから助けてほしい。支援が欲しい。
そう話して「ごめんなさい」と言われる。
それは、「あなたが死にそうでも、どうすることもできません」「死んでしまっても仕方ないのかもしれない」というメッセージに等しかった。
そして、見てわかるほど痩せ、友人に「また痩せたね」と言われ続けた日々を過ごした。生存するための飲食も排泄も睡眠も服薬も後回しにしたからこそ、生存をこなした。生存するために健康を蔑ろにするという矛盾にある日々を、だれなら理解してくれますか。
それでもわたしは死ななかった。
理由はたぶん、わたしが「解離性同一性障害だから」に尽きる。
本当に死んでしまうかもしれないくらいの状況になると、死なないための行動に徹し始める。何もできないのに、栄養と水分を摂取する。生存するために必要なことをこなす。
わたしは「解離性同一性障害」であることで困っている。でも、「解離性同一性障害」であるおかげで、生存をしている。
英語学習という生存戦略
学ぶことで、わたしは生き延びた
支援が止まっていた間、わたしはXに英語用のアカウントを作り、英語学習アプリのDuolingo(デュオリンゴ)を始めた。
デュオリンゴは、無料で語学を学べるアプリだ。その仕組みは、世界のどこかにいる誰かが課金することで成り立っている。「学びたい」と思う誰かのために、別の誰かが支払っているのだ。
日本は、個人による寄付が世界でもっとも少ない国のひとつだと言われている。
語学学習アプリについて日本語で検索しても、デュオリンゴは「無料で全部使える」としか書かれていない。
なぜ無料なのか、それを可能にしている仕組みについて語る人は、ほとんどいなかった。
中には「無料だから課金する必要はない」とまで書く人もいる。
そういう言葉を見るたびに、「そうじゃないんだよ」と思った。
わたしは、食事も水分も摂れず、立ち上がる力さえ出なかった日も、英語学習だけは欠かさなかった。
Duolingoを始めてから今日で88日目。
この数字はただの記録じゃない。わたしが、生きようとしていた証だ。
学ぶということは、わたしにとって“生きること”と同義だった。
「食べて、飲んで、排泄して、眠る」ことが生存の条件なら、
「つながり、希望を持ち、成長すること」は、わたしにとっての生命維持装置だった。
国際的コミュニティの支え
日本語での発信は、「精神障害者」というレッテルを通して読まれがちだった。
支援を受けて生きていることを、揶揄されたり、見下されたりすることが多々ある。
でも、英語圏のXでは違った。
そこでは、わたしの言葉だけが届いた。
誰もレッテルでわたしを判断せず、「あなたが生きていることを誇りに思う」「あなたの言葉は素晴らしい」と声をくれた。
その言葉たちが、わたしの“生”を肯定してくれた。
新しい相談支援員との出会いと再スタート
そうして今、ようやく動き出せる
今週のはじめからヘルパー利用が再開された。
新しい損段支援員は、脳性麻痺を患う男性だ。発語が難しい状態だが、こちらの聞く姿勢次第で聞き取れる。彼の第一印象は福祉に携わる誰に聞いてもその発語の「うわわわ」というものだった。でも彼はわたしの話を誰より真剣に聞いてくれた。
「ぼくは障害者です。ぼくは障害者の味方です」
この言葉がどれほど心強く感じたか。そして、彼が相談支援員の資格を持っていること、そもそもの事業所を彼が立ち上げたという話に尊敬の念を持つと同時に、彼が奮起したことの背景を想像して言葉にできない思いになった。
彼は市役所で支援会議を開いた。
わたしと、ヘルパー事業所を二社、そして福祉課の生活支援のケースワーカーを障害支援課の担当者、地域包括支援センターから二人、そんな顔ぶれで、これからのわたしの生活をたくさんの人がかかわる形で支えていくと、彼が言った。
OFUSE導入とZINEの立ち上げ
わたしはこのブログを収益化をめざして立ち上げた。
けれど、広告収入として最もメジャーなGoogleアドセンスを入れたなら、日本ではおそらく性的な広告が表示されることを避けられない。
わたしはこのブログで性暴力についての情報を自分の経験を元に発信したい。それを当事者に届けたい。だから、そんな広告は絶対に表示させたくない。
でも、性的なものを排除した広告会社では、おそらくこのブログの内容では審査に通らない。そもそもセンシティブな話題のブログは広告導入の審査に通りにくい。
そこで、OFUSEというサービスを使って、支援を募るという形を考えました。
それとBuy Me a Coffeです。
もし、わたしのこのブログに賛同して頂けるなら、わたしの言葉に価値を感じるなら、あるいはわたしの未来への投資をして、支援をお願いします。
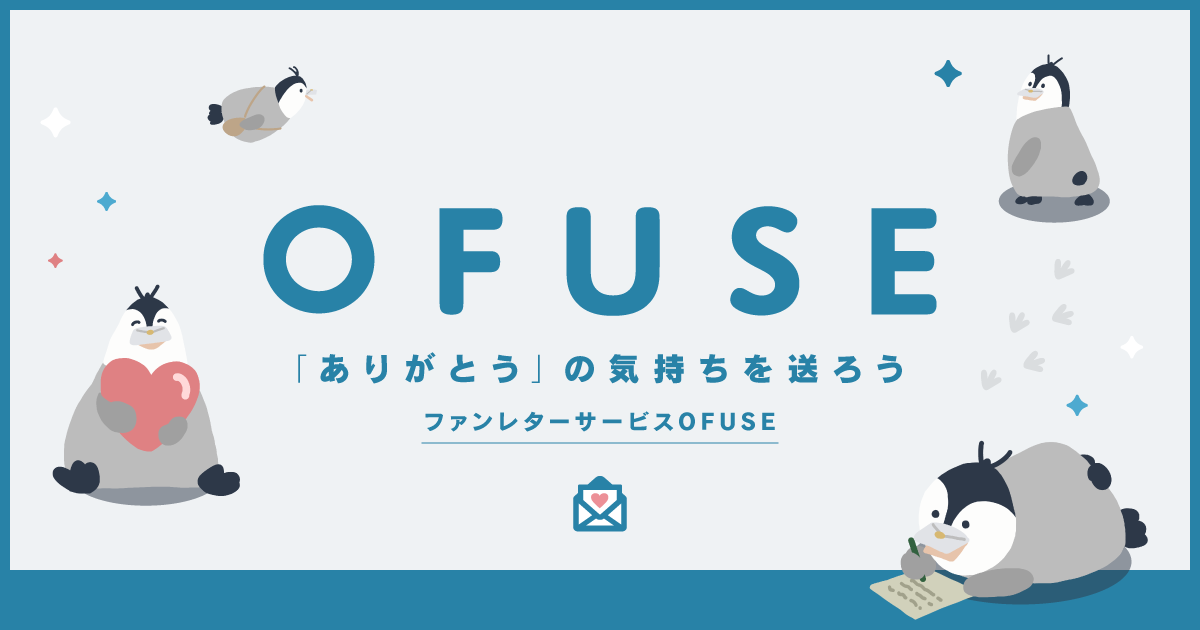
OFUSEでは、いまはまだ準備も出来ていませんが、返礼品のようなものもできたらと思っています。
幸いなことに、わたしはイラストを描けるので、それをポストカードにしたり、そんな形を考えています。
また、ハンドメイドのいろいろもそこそこ得意だったりするので、そうしたものを販売することも考えています。(多趣味ですべてを深く掘り下げてきたことが活かされる!?)
そして、もうひとつ。ZINEで発信していくことをしようと思っています。デジタル媒体、kindleで無料でと考えています。ブログよりもっと掘り下げていく形で。また、希望する方がいたら、紙媒体のものも都度発行したいなあと。
「どうか、あなたの目に届きますように」
この国は、問題を「答えの出せる人」だけが話すことを求めます。
でも、答えのない問題が、いまこの社会を蝕んでいます。
「支援が止まってしまった人が、そのまま取り残されること」
「生きているだけで精一杯の人に、なお“自己責任”を押し付けること」
これは誰にとっても無関係な話じゃない。
わたしはまだ、これにどう答えたらいいのかわかりません。
でも、だからこそ、わたしはこう問いかけたい。
――“生きる”って、なんですか?
わたしは、トラウマや精神的困難を抱えて生きる当事者として、社会の中で見えにくい声を可視化したいと思っています。
このブログは、そのための発信の場です。
それは同時に、自分の生きづらさと向き合う日々の記録でもあります。
制度の隙間で取り残されるような立場だからこそ、発信を続ける意味があると信じています。
その営みは必ずしも「収益」につながるものではありませんが、社会にとって価値のある言葉だと信じて書いています。
支援というかたちで、この取り組みに参加してくださる方がいたら、とても心強いです。
ご支援は、ブログ運営の継続や、取材・表現のための資源として大切に使わせていただきます。
もし共感していただけることがあれば、OFUSEやBuy Me a Coffeeなどを通して、応援していただけたら嬉しいです。
「わたしにはあまりに選択肢がありません。なので、わたしは選択肢をつくるという選択をしました。それはわたしのような存在にとってもっとも険しく、けれど最も希望ある選択肢なのです」―ハココ(1985年~)
さあ、ハココ!RE STEART!