ポスト構築主義の限界と社会的現実の責任:バトラー理論が現実にもたらすもの
ー
わたしはジュディス・バトラーの著作を直接読んではいません。
したがって、これはバトラー理論の学術的検証ではありません。
しかし、バトラーの名のもとに展開されている現代の言説——それは欧米で10年にわたる深刻な社会問題を引き起こし、多くの若者に不可逆的な医療介入をもたらしました(英国Tavistock Clinicの閉鎖、北欧諸国の方針転換など)——への批判として、これを書きます。
理論の正確さよりも、現実の身体と人生が問題です。
そうして日本は今、その帰結が明らかになった後であるにもかかわらず、10年遅れで同じ轍を踏もうとしています。
「セックスは常にすでにジェンダーである」のか?
ジェンダー理論は、「セックスはジェンダーによって構築される」と主張することで、身体的性差を言語的・社会的な意味づけの産物と位置づける。これは、ポスト構造主義的な前提に基づき、主体や身体そのものが言説によって生成されるとする立場である。
(これがわたしの理解です。)
この理論は、確かに哲学的には一貫している。人間の存在や思考が流動的であること、昨日の自分と今日の自分が同一であることの証明が不可能であること、そして言語が世界を構成するという視点は、思考実験として理解可能である。だが、思考実験そのものを現実とみなすことは、社会の維持を不可能にする。なぜなら、それは「何でもあり」を許容することになり、共通の認識や制度的安定性を破壊するからである。
極端な比喩を用いるならば、
バトラーの論理は「人間がとある果実をリンゴと名付けたからリンゴである」とするものである。そして、「オレンジという果実も人間がオレンジと命名したからオレンジとして存在する」のだが、現実にはオレンジはリンゴとは異なる物として存在している。それらを「リンゴ」としたのも「オレンジ」としたのも人間の言語と思考による命名にすぎない(つまりはどちらもリンゴでもオレンジでもあることが可能だった)が、両者の物理的構造や味、栄養成分、育成環境などには明確な差異が事実として存在する。だからこそ、別の命名をされており、別の意味付けがされたのだ。つまり、意味づけが可能であることと、物理的事実が存在しないことは同じではない。
バトラーの構築主義は、言語による意味づけの力を過度に強調するあまり、身体的現実や制度的暴力の分析を空洞化する危険を孕んでいる。身体性は、言語による命名以前に人間に作用する現実である。出産、痛み、老化、障害といった身体的経験は、社会的意味づけを超えて存在し、制度的抑圧の根拠ともなりうる。これらの現実を「言語によって構築されたもの」として扱うことで、むしろその抑圧の実態を見えなくしてしまう可能性がある。
哲学は、科学や制度の前提すらも疑うことができる。しかし、社会はそのような懐疑を前提にしては成立しない。言語の意味がある程度共有されていること、他者との関係性が継続しているとみなされること、法や制度が一定の前提に基づいて運用されること、科学的知識が再現可能であると信じられていること――これらはすべて「思考実験では崩せる」が、「社会的現実としては必要不可欠」なものだ。
したがって、バトラーの言説に説得力を感じられないのは、単なる理解不足ではなく、身体的現実と意味づけの関係をめぐる哲学的誠実さに基づいた批判的姿勢である。構築主義が現実の差異を無化することで成立しているとすれば、それは解放の理論ではなく、現実の暴力を覆い隠す理論である可能性すらある。
構築主義の欠損と多様性論の矛盾
くり返しになるが、
ジュディス・バトラーのジェンダー理論は、「セックスはジェンダーによって構築される」と主張することで、身体的性差を言語的・社会的な意味づけの産物と位置づける。これは、ポスト構造主義的な前提に基づき、主体や身体そのものが言説によって生成されるとする立場である。
だが、この理論には重大な欠損がある。バトラーの構築主義は、「生物学的差異が社会的役割を方向づける」という前半の現実を欠いたまま、「社会的役割が生物学的差異を構築する」という後半だけを強調している。この逆転構造は、現実の身体性や制度的抑圧の分析を空洞化する危険を孕んでいる。
現実には、出産や身体的特徴といった生物学的差異が、性役割の形成に影響を与えている。資本主義的分業体制の中で、これらの性役割は制度化され、再生産される。つまり、生物学的差異 → 性役割 → 制度的再生産 → 生物学的差異の強化という構造が存在する。
バトラーの理論は、この出発点を欠いたまま、構築の論理だけを展開しているため、現実の分析としては不完全である。
さらに、バトラー理論を支持する一部の多様性論者には、論理的な矛盾が見られる。彼らは「生物二元論を否定する」と言いながら、「性別をトランスする」ことを肯定する。だが、性別を「移動可能なもの」とするには、出発点としての性別が存在していなければならない。否定したはずの二元論に依存して、トランスの語りが成立しているのである。また、「性別はグラデーションである」と主張しながら、「あなたとわたしは同じ女性ではない」とすることを認めない態度も、理論的に破綻している。
グラデーションを認めるならば、同じ「女性」というカテゴリーの中に多様な差異が存在することも認めなければならない。差異を認めることなく多様性を語ることは、単なる同質性の強制であり、理論的にも倫理的にも矛盾している。
哲学は、存在や主体の不確かさを問い直す力を持つ。だが、思考実験そのものを現実とみなすことは、社会の維持を不可能にする。言語が世界を構成するという視点は理解できるが、意味づけが可能であることと、物理的事実が存在しないことは同じではない。社会は、共通の認識と制度的安定性を前提として成立している。構築主義がその基盤を揺るがすとすれば、それは解放の理論ではなく、現実の暴力を覆い隠す理論である可能性すらある。
バトラーの構築主義は、言語による意味づけの力を過度に強調するあまり、身体的現実や制度的暴力の分析を空洞化する危険を孕んでいる。身体性は、言語による命名以前に人間に作用する現実である。出産、痛み、老化、障害といった身体的経験は、社会的意味づけを超えて存在し、制度的抑圧の根拠ともなりうる。これらの現実を「構築されたもの」として扱うことで、むしろその抑圧の実態を見えなくしてしまう可能性がある。
したがって、バトラーの言説に説得力を感じられないのは、単なる理解不足ではなく、身体的現実と意味づけの関係をめぐる哲学的誠実さに基づいた批判的姿勢である。構築主義が現実の差異を無化することで成立しているとすれば、それは解放の理論ではなく、現実の暴力を覆い隠す理論である可能性すらある。
構築主義の限界と現実への責任
身体・制度・多様性をめぐる三つの問い
「身体性の現実」と「言語の構築性」の境界
ポスト構造主義的ジェンダー理論は、言語が主体や身体を構築すると主張する。ジュディス・バトラーは、セックスすらもジェンダーによって意味づけられた構築物であるとするが、この立場は、身体性の現実を過度に抽象化する危険を孕んでいる。
メルロ=ポンティの現象学は、身体を「世界との接点」として捉え、言語以前に身体が世界に触れていることを強調する。
アーレントは、人間の活動が「労働」「仕事」「行為」に分かれることを示し、身体的必要性が政治的言説とは異なる次元にあることを明らかにした。
これらの思想は、身体が言語によって構築される以前に、すでに世界に現れているという事実を回復する。構築主義がこの前提を欠いたまま言語の力を絶対化するならば、それは現実の身体的苦痛や制度的抑圧を見えなくする理論でしかない。
「制度的暴力」と「言説的暴力」の違い
バトラーは、言説が暴力を構成することを論じるが、制度的暴力の物理性を十分に扱っていない。たとえば、福祉制度における性別分業、医療制度における診断基準、教育制度における性別役割の固定化などは、言語的意味づけを超えた物理的・経済的な暴力として作用する。
制度的暴力は、身体に直接的な影響を与える。それは、住居の喪失、医療の拒否、就労の排除、教育機会の剥奪といった形で現れる。言説的暴力が「語られ方」の問題であるのに対し、制度的暴力は「生き方」そのものを制限する。
構築主義がこの制度的暴力を「言説の問題」に還元するならば、それは暴力の実態を理論の外に置くことになる。制度の物理性を見失った構築主義は、現実の苦痛に対する責任を果たさない。
「多様性の名による同質性の強制」という逆説
現代のアイデンティティ政治は、「多様性」を掲げながら、しばしば同質性の強制を行っている。性別はグラデーションであると主張しながら、「あなたとわたしは同じ女性ではない」とすることを認めない態度は、差異を認めることなく多様性を語るという逆説に陥っている。
また、生物二元論を否定しながら、性別を「トランスする」語りを成立させることも、理論的に破綻している。トランスという語りは、出発点としての性別を前提とするが、その前提を否定してしまえば、語りそのものが成立しない。
多様性とは、差異を認めることであり、同一性を強制することではない。「多様性の名による同質性の強制」は、倫理的にも理論的にも矛盾している。それは、自由の名のもとに他者の語りを封じる暴力であり、構築主義が見落としがちな倫理的責任の問題である。
哲学的構築と言語的混乱の交錯
ジュディス・バトラーは、哲学者としての顔と巧みな言語操作によって、ジェンダー理論における構築主義を展開した。彼女の主張は、セックス(生物学的性別)すらもジェンダーによって構築されるとするものであり、主体や身体の安定性を根本から揺るがす。
彼女の言説は、哲学的思考と政治的言語の境界を巧みに撹乱する。抽象的な言語を用いて、意味の不安定性や主体の流動性を語る一方で、現実の制度や身体的経験に対する責任を回避する。これは、哲学的構築と政治的混乱の交錯によって、議論の地盤を意図的に曖昧にする戦略である。
バトラーの理論は、哲学的には興味深いが、社会的現実に対する責任を果たしていない。言語による構築の力を過度に強調することで、身体性の現実や制度的暴力の物理性を見えなくしてしまう。哲学は混乱を生むためにあるのではなく、現実を照らすためにある。その意味で、バトラーの言説は、哲学的誠実さよりも言語的技巧に依存した、危うい構築物であると言える。
言語の力と哲学の暴力
ジュディス・バトラーは、ポスト構造主義の枠組みの中で、言語が世界を構成するという思想を展開した。彼女の理論は、主体や身体、セックスまでもが言語によって構築されるとするものであり、言語の力を絶対化する傾向を持つ。
しかし、この言語観は、ポスト構造主義が発見した「言語による世界の構成」という洞察を、ある意味で雑に扱っている。バトラーは、言語が意味を生み出すという事実を、現実の身体性や制度的構造を無化するための道具として暴力的に利用しているように見える。これは、言語による社会の破壊の試みであり、現実世界への抵抗という名のもとに、幻想を現実とする哲学の暴力的解釈と使用である。
言語は確かに、世界に意味を与える。しかしそれは、現実の物理性や身体性を否定することとは異なる。言語が世界を構成するという思想は、現象学的には「現れ方」の分析であり、現実の消去ではない。バトラーの言説は、この区別を曖昧にし、言語の力を過度に拡張することで、現実の制度的暴力や身体的苦痛を理論の外に置いてしまう。
このような言語の濫用は、哲学の名を借りた混乱の生成であり、哲学的誠実さよりも言語的技巧に依存した危うい構築物である。哲学は、現実を破壊するためにあるのではなく、現実を照らし、問い直すためにある。バトラーの言説がその役割を果たしていないとすれば、それは哲学の暴力的使用であり、倫理的にも理論的にも批判されるべきである。
哲学は、現実を問い直す力を持つ。しかしその力は、現実を破壊するためではなく、照らし出すために使われるべきである。言語が世界を構成するという思想は、現象の「現れ方」を分析するためのものであり、物理的現実を消去するための道具ではない。
バトラーの言説が、言語の力を過度に拡張し、身体性や制度的暴力の現実を理論の外に置くならば、それは哲学の暴力的使用であり、倫理的にも批判されるべきである。
最後に
わたしはこう問いかけたい。
ここにリンゴがあります。
いいえ、これはオレンジでした。
いま、言語によって再定義されたそれは、何として存在しているのでしょうか。
あなたの目の前にあるその果実は、いま、何ですか。
もしあなたがその果実をオレンジだと認識できないとしたら、それはなぜですか?
その認識の構造をなぜ性別にだけは適応できるとしているのですか?

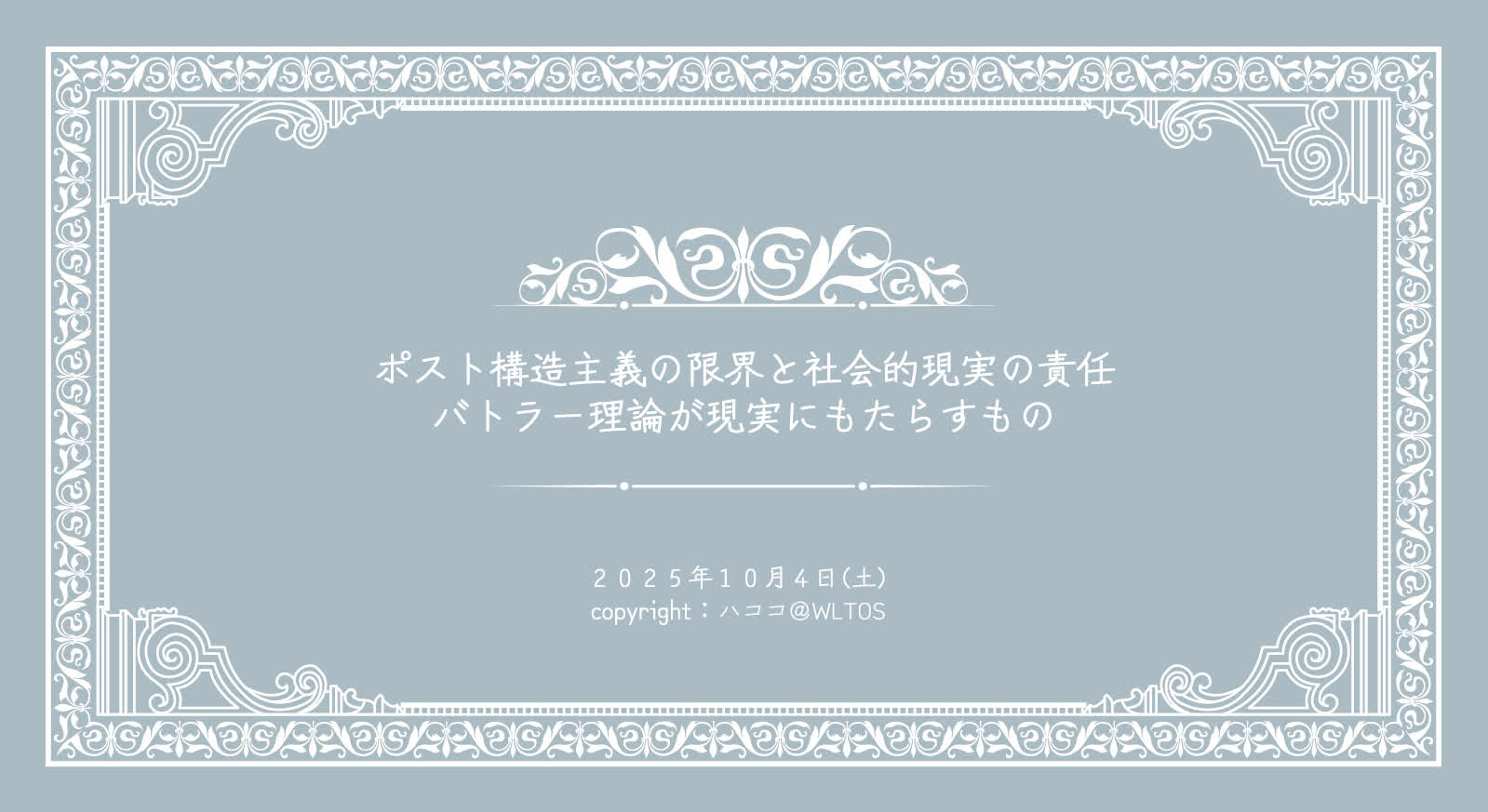

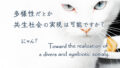
コメント