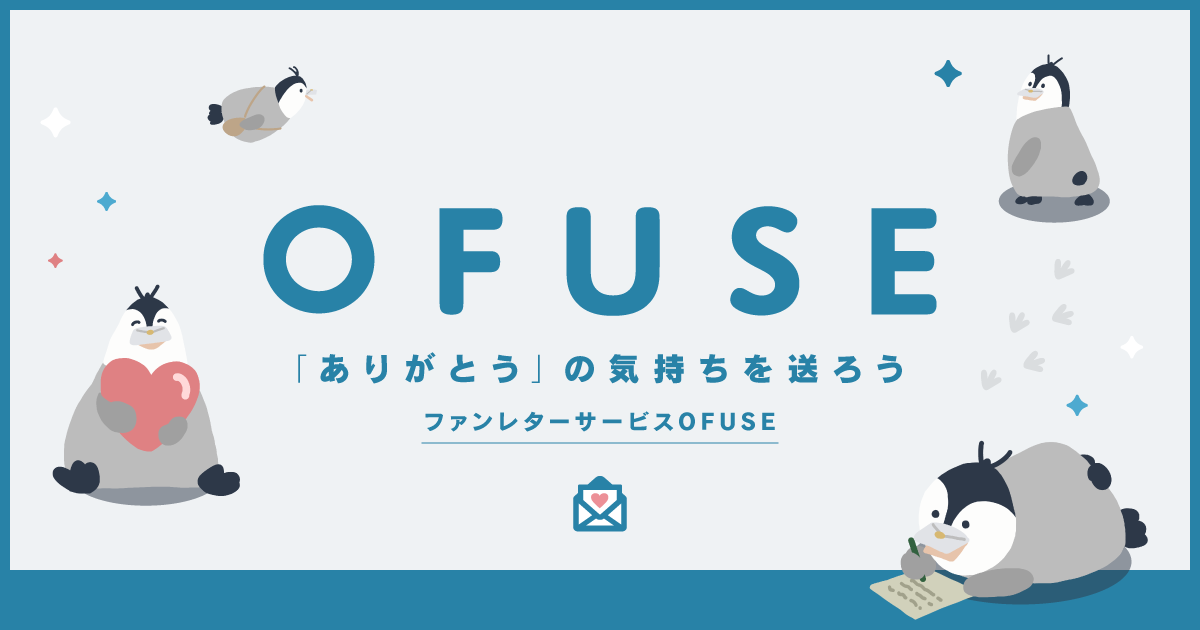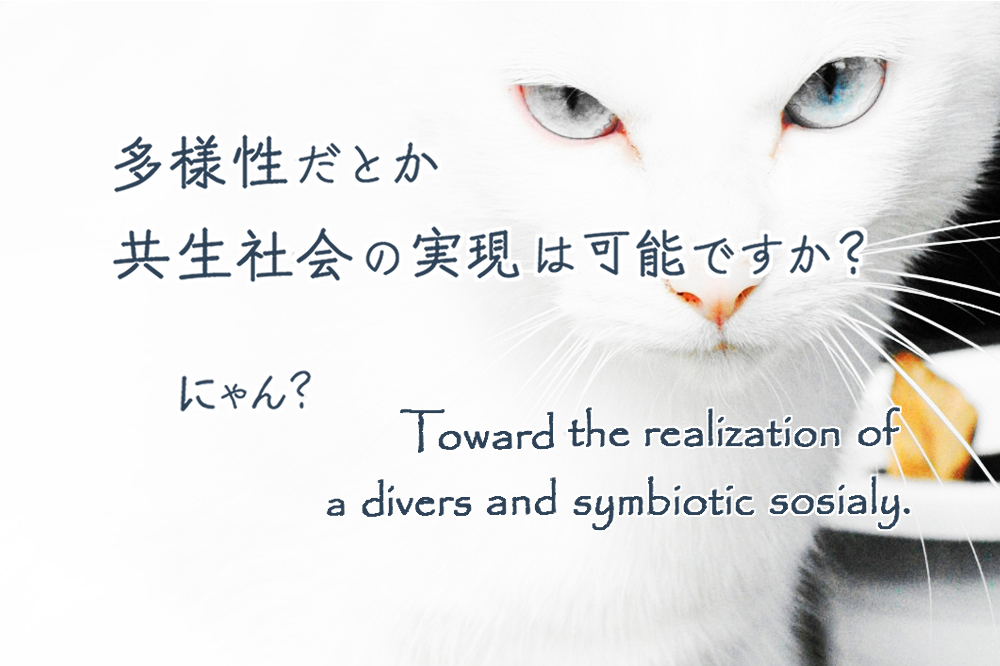社会福祉への投資にはリターンしかない
ー

【精神障害者家族の生産性低下で経済損失、年2兆円超 全国団体が初の推計】
精神障害者と同居する家族の労働生産性が低下したことによる経済的な損失が、全国で年間2兆円を超えることが、このほど、全国精神保健福祉会連合会(岡田久実子理事長、みんなねっと)の初の推計で分かった。
精神障害のある人のケアを家族に依存する実態はこれまでも問題視されてきたが、同連合会は経済的な損失も示すことにより、家族支援の必要性を広く訴えていく考えだ。
推計のもとになる調査は2024年12月~今年2月に実施。家族会未入会者を含め1619票の有効回答を得た。就労する家族には、自身の仕事の生産性の変化を11段階で評価してもらった。
その結果、本人が発症した後の家族の労働生産性は、平均で通常時の半分になることが判明。それをもとに算出すると、就労家族1人につき年間で平均119万5000円の損失となる。65歳未満の精神障害者と同居する全国の家族の半数(約191万人)が就労していると仮定したところ、損失額は2兆2878億円に上る。
また、回答者全体の49%が本人の病気や体調のため勤務時間を短縮したり、転職したりしたと回答。就労している家族の年収が、一般就労者より低いことも分かった。
回答者全体の約8割が十分に睡眠をとれないなど身体面で不調を感じ、約3割が精神科を受診するなど精神的な不調を抱えていることも分かった。
報告書は「家族自身も困難を抱えていることは長年指摘されてきたが、問題は見過ごされ、家族が孤軍奮闘している実態が明らかになった」としている。
「福祉新聞」2025年10月16日の記事
この記事をわたしはXにて引用し、自分の考えを述べた。
(以下、全文)
イエ単位での介護の限界。個人の問題ではなく、家庭の問題でもなく、個人の疾病や障害については、社会的な課題である。社会を維持するために、福祉の充実が必要なのだ。福祉に財源を割くことこそが社会の維持・発展に寄与する。福祉にはリターンしかない。
福祉の財源を割くことで、経済的な損失がある。財源がないから福祉にお金をまわさないとして、それが本当に未来をつくるための政策として良いものとなるのだろうか?社会に強者しかいないなら、それで構わない。けれどそれは社会とは呼ばない。
経済が低迷する中で増税をするなら家庭の財布の紐は緩くなるはずもない。使えるお金が減るのだから消費傾向は減少する。消費の減少とは、単に物を購入する、余暇を愉しむことだけではない。教育資金、自身への投資、未来をつくるための支出にも消極的になる。根性論では社会維持も発展できない。
そんな中で福祉に財源を割くことは国民の悪感情を誘うだろうか。しかし、福祉の不足によってむしろ経済損失が増加する。社会的な損失がある。欧米での福祉の充実は、これら損失への対策である。目先のことではなく、未来のために社会福祉に投資をしているのだ。
精神疾患の家族に焦点が当てられるのは、さすがはイエを重視する社会制度を維持している日本といったところか。しかし、実際は家族の生産性だけ終わらない。福祉の不足は貧困の連鎖を生じさせ、それは経済損失として社会にかえされる。経済損失が連鎖していくのだ。
経済損失をうむのは、疾病と障害者支援のための支出ではなく、むしろ疾病や障害者への支援の不足である。それらは貧困を連鎖させ、経済損失を再生産し、社会の維持・発展にネガティブな影響を与え続ける。
そのために必要なことは排除か?
それとも対策だろうか?
今の日本は何をしている?
非虐待サバイバーや性被害サバイバー。彼ら彼女らはその逆境から抜け出した後に、加害者から受けた加害の影響での症状に苦しむ。社会生活を送ることが困難になるほどの症状に苦しむその疾患、障害の名はPTSD(複雑性PTSD)や解離性障害。しかし現代日本では障害年金の対象ですらない。
犯罪行為として認められることもない虐待の影響を、実際には犯罪と同等かそれ以上の加害を受けたのに、サバイバーは個人で引き受けることになる。そんな彼ら彼女らにあまりに社会は冷たい。
日本が心的外傷の支援に力を入れないのはなぜか?
財源がないからか?
だとして、負の連鎖は社会的な経済損失として社会にネガティブな影響を与え、その損失を再生産することにもなる。
ベトナム帰還兵のPTSDを転換点としたアメリカと、自国の帰還兵を放置した日本。その岐路はどこにあったのか。
たとえば、イエ制度は家庭の問題として扱うことを正解だとし、問題を矮小化し、責任の所在を欺き、社会の経済的損失とその責任から目をそらすように仕向けることも可能だ。
家庭内の問題は本当に個人の問題として片付けられるのか?
社会の対応、福祉の不足は、経済損失として社会にかえされるのに?
福祉はリターンがなくても行うのか?
かつて、Xのスペースで福祉の財源について話す専門家の配信を聞いていた。
アナログゲーム療育を提唱する専門家が、福祉の財源について語っていた。
それを聞いていた元放課後デイの支援者が、のちに自分のスペースでこう語った。
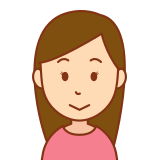
福祉の話をするのに財源から逃げないのは素晴らしい!
わたしもその配信を聞いていた。しかし、わたしが聞いたのは「財源がない」という現状の確認と、「だからできない」という嘆きだけだった。
財源を確保するための具体的な提案はなかった。
そこで、彼女のスペースに参加し、問うた。

どこに財源から逃げていない姿勢がありましたか?財源がないという確認だけで、確保するための現実的な提案はなかった。財源がないからできないことばかり……と話していただけで、財源と向き合っているとは言えないのでは?

本当に財源の話から逃げないのであれば、財源がないから厳しいという話ではなく、政治からどうやって財源を引き出すか、福祉のリターンの説明をすべきでは?
しかし、わたしのこの問いかけに対して、彼女はこう返してきた。
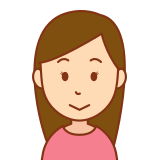
あなたはどういう立場から物を言ってるのか?あなたはこのことで何を行えているのか?
わたしは答えた。「わたしは福祉がなければ生活できない、社会の底辺にいるものです」
彼女は応えた。「あなたが実際に何かしているなら応援したいのだけど、私は大変すぎるからやらない」
「財源がない」という言葉の重さは、立場によってまったく違う
わたしはこう続けたい。

あなた方は支援がなくても生きていけるし困らない。わたしたちは支援がなくては生活できない。財源がないという残酷さをあなたはわかりますか?
そして、わたしは問い返した。

このことで意見をいうことに資格でもありますか?わたしはリアルに自分事でしかないのです。なぜわたしの立場を説明する必要がありましたか?
彼女は答えなかった。未だに、その答えはもらえていない。
そして、「他の人が話したがっているから」と、わたしは引き下がるよう促された。
答えられないこと自体が、答えだったのか
彼女がわたしに「立場」を問うたのは、発言権を剥奪するためだったのではないか。
当事者としての批判は、彼女たちの「理解ある支援者」という自己像を脅かす。
でも、わたしには最も強力な「資格」がある。当事者性というものだ。
福祉について語ることに、どんな資格が必要なのか?生存がかかっている人間の声を、なぜ制限できると思うのか?
彼女は答えられなかった。なぜなら、答えようがないからだ。
支援者にとって「財源がない」は、残念だが仕方ない「制度の限界」。
当事者にとって、それは生存の危機だ。
同じ言葉を語っていても、その重さは天と地ほど違う。そして、その違いを理解しないまま「財源について語っている」と自負する人々がいる。
彼らは財源から逃げている。ただ、それに気づいていないだけだ。
そこは、社会問題への「理解」を深める場だった。実際の変革には踏み込まない、安全な批判の場だった。「財源がない」と嘆き合い、「でも仕方ない」と確認し合う場だった。
当事者の声は歓迎される。ただし、彼らの自己像を脅かさない限りにおいてのみだ。
わたしたちは常に、「良い当事者」として語ることを期待されている。自分の苦しみを語り、彼らの善意に感謝し、彼らの「理解」を称賛する。でも、彼らの姿勢を批判しない。
わたしはそうしなかった。だから、排除された。
要するに、わたしは、彼らの「サークル活動」を邪魔したらしい。
これが、日本の福祉言説の現実だ。
「福祉を語る人々」の多くは、当事者を「テーマ」として消費し、自分の善意を確認し、でも変革はしない。
そして、その構造を指摘する当事者は、「場を乱す者」として排除される。
人権的な観点から話すなら、福祉はリターンがなくても行うべきなのかもしれない。
しかし、それは資源や財源が有限であることを考えたとき、果たして現実的だろうか?
人間は何のリターンもないのに、他者のために真剣になることができるだろうか?

でも……、リターンのない社会福祉なんてものが、あるのかな?
わたしにしてみれば、福祉にはリターンしかない。
お金として返還されるものではなくとも、人の心理面の充足や、社会秩序のため、公衆衛生のため、人が生きるということの基本、つまりは人権そのものの実践が福祉だと思う。
人権を尊重することにリターンがないとは、一体どういうことだ?

まさか、現金としての生産性をリターンだと思ってたりしないよね……?
「リターンがないからやらないということに繋がる」
福祉を行う人がそんな文言を口にしたことにわたしは衝撃を受けた。
生活保護と国民皆保険は日本の福祉の優秀さなのか?
なぜ、彼女たちは「財源がない」という残酷さを理解できなかったのか。なぜ、当事者の声を「立場」で制限しようとしたのか。
それは個人の問題ではない。日本の福祉システムそのものの構造的欠陥だ。
専門性の欠如——日本独特の問題
知ってほしいことがある。
福祉の専門知識がない人間に社会福祉の業務を行わせているのは、日本独特だ。欧米では福祉の専門職だけが、その業務を担当している。
それがなぜだか分かるだろうか?
社会福祉を頼らざるを得ない人というのは、普通を普通に享受できない人たちである。
それはその個人の課題ではなく、社会的な不平等、不公正から来るものであり、それは社会的な課題であり、個人の自己責任に還元されるべきではない。
そして、普通を普通に享受できてしまえている人たちにとって、社会福祉に頼らなければ生活困難であるということがどういうことなのか、想像もできないからだ。
つまり、普通とは、ある意味、特権なのだ。
特権から来る暴力
特権から来る発言は不用意なものだ。
普通を普通に享受できた人たちに、普通を普通に享受できないことの困難は想像ができない。いつだって、想像をしたつもりになっているだけだ。
日本で社会福祉を担っているのは、単なる地方公務員である。
彼らは法律で定められた制度を市民に説明するが、その法的根拠は説明できない。なぜなら彼らは法律を学んではいないからだ。
また、彼らは異動することが前提の地方公務員だ。
福祉課に異動して、初めて福祉の「業務」を知る。行う。付け焼き刃の知識で、マニュアル業務を行う。
本当は何が行えて、何を行えないのかを、彼らは知らない。知っているのは、制度の条文だけだ。
福祉の理念ではなく、制度を行うだけの福祉課という担当部署が、日本の社会福祉の砦である。
屈辱から始まる「支援」
そこでは日々、自立支援とは名ばかりの、自己責任論が横行している。
水際作戦は有名だが、それだけではない。
なぜ水際作戦が行われるのか。それは生活保護から抜け出せなくなるのが、生活保護の仕組みだからだ。しかも抜け出せないのは、個人の努力が足りないからではない。制度として、自立のための支援になっていないからだ。
そして、嵩む社会保障費を削るべく、受給させない方向に動く。
社会福祉は生存権だ。人の尊厳の話である。
しかし、日本の社会福祉は、疲れ果てた人に客観的事実の提示を求め、自分が困窮者であることを証明させ、その屈辱を味わわせるところから始まる。
「屈辱を飲み、人間としての当たり前を捨てて、それでも生きていたいですか?」
極端に言えば、そう問われることが、日本の社会福祉である。
男性の自殺率の高さは、困窮した男性に対する社会的に冷たい扱いだけが原因ではない。自尊心を捨てるように迫る社会に、彼らはその生命をもって抵抗しているのかもしれない。
ただ、女性はプライドを捨てでも生きていけるのかと言えば、そういう話ではない。単に、社会福祉に頼る女性の多くが、守るべきもののために頼るから、自分のプライドより優先すべきものがあるということでもあると思う。
自己責任という言葉の本当の意味
自分の言葉や行いに責任を持つ——それだけのことだったその単語は、今や一人歩きしている。努力不足を指摘するために使われる。
実際にどれだけの努力をしたのかは顧みられることもない。どこの地点から歩き出したのかさえ、顧みられることはない。
普通をはじめから享受できる人たちが、普通を初めから得るチャンスさえなかった人たちに「自己責任論」を押し付ける矛盾に気づけないことが、普通を普通に得られた人たちの「特権性」である。
スタートラインの位置はその人の責任ではない。はるか後方からのスタートであることを乗り越えられないことも、その個人の責任ではない。ましてやそれを努力不足と断じることなどあってはならない。
これが、あのスペースで起きたことの本質だ。
「あなたはどういう立場から物を言ってるのか?」「あなたは何を行えているのか?」
彼女たちは、特権の中から語っていた。「財源がない」という言葉の重さを、本当には理解できない立場から。「大変すぎるからやらない」と言える立場から。
そして、わたしのような当事者が構造を指摘すると、「場を乱す者」として排除する。
これが、日本の福祉の現実だ。
どんなリターンがある?
それはもう、ありとあらゆるリターンがある。
- 社会秩序に貢献する
- 公衆衛生に貢献する
- 社会的な経済損失削減に貢献する
- 社会的な経済利益に貢献する
逆にデメリットは何があるかと言うと……、実は無い。社会福祉の充実にデメリットなんてものはないのだ。
社会福祉は社会に生きる人の権利の指標
社会福祉に財源を割くことを、財政の圧迫としてしか捉えられないのは、ナンセンスだ。
そもそも、社会福祉が充実していないということは、足りなければ足りないほど福祉の助けが必要な人たちは福祉がなくても生活していけるようにはならない。それどころか、より良い生活になるのではなく、悪化の可能性のほうが高いだろう。
福祉が必要な人は社会的弱者だ。社会的弱者は個人の努力でどうにかなる困難ではなく、社会構造として、あるいは社会制度に阻まれているから、弱い立場にある。とりわけ経済的に。
しかし、その社会的弱者にも家族がいる。イエ制度が基本で、家庭のことは家庭で、とする日本で、疾病や障害を抱えて生きる当事者の介護が重くのしかかる。福祉の足りなさが、その家庭全体での生産性の落ち込みへとつながり、さらにはそこから立て直すことも難しくなる。
もし、その当事者に子どもがいたなら、その子の人生にも影響が出る。選択肢が極度に狭まり、メンタルヘルスに課題を抱えることになるかもしれない。そして、福祉に頼らざるを得ない状況が再生産される。
冒頭の記事にあるのは、そうした連鎖の一部である。
社会を一つの企業として考えてみる
ここで、日本社会を一つの企業だと想像してみてほしい。
福利厚生がしっかりしている企業と、そうでない企業。どちらで働きたいだろうか?
福利厚生が充実している企業は働きやすく、将来的な不安も少ない。それは就職先を選ぶ重要な指標だ。たとえ仕事の難易度や役職が違っても、「福利厚生がしっかりしている」という点では全員が同じ恩恵を受ける。
逆に考えてみよう。福利厚生が不十分な企業で、同じように熱心に働けるだろうか?
「会社のプロジェクトのために福利厚生を削る」と言われて納得できるだろうか?
賃金カットを繰り返し、福利厚生を減らし続ける企業に未来があると思えるだろうか?

働いてるんだから福利厚生は当たり前だろ。社会のお荷物の話とは無関係だ。
本当にそうだろうか?
日本という社会を、あなたが所属する企業だと考えてみてほしい。社会で生活することは、言わば企業で働くことに似ている。
福利厚生がなってない企業に未来があると思えるだろうか?
賃金カットを繰り返し福利厚生を減らすことに納得できるだろうか?

だからってどうすることもできないじゃん……。
本当にそうか?
確かに、あなたが一従業員ならそうかもしれない。
しかし、日本は民主主義であり、主権者は国民だ。つまり、このたとえで言うなら、わたしたちは企業のトップか、それに準じる役職として、経営陣に物を言える立場にいる。
日本社会だって、福利厚生はしっかりしておいてほしくないだろうか?
単純に比較できるものではないが、社会に福祉が足りないということは、福利厚生が不十分な企業どころか、ブラック企業だと言える。
社会福祉について考えよう
「福祉はコストではなく投資である」という本質
冒頭の記事にある2兆円超の経済損失は、福祉の不足そのものが生み出している数字です。支援することで生じる損失ではなく、支援しないことで発生している損失です。この視点の転換が決定的に重要です。福祉支出を「社会のお荷物」として語る言説は、実は最も高くつく選択なのです。
- 家族の生産性低下
- 貧困の連鎖
- 次世代への影響
- 犯罪や社会不安のコスト
——これらを合算すれば、適切な福祉投資の何倍ものコストを社会は払い続けることになります。
イエ制度による問題の「私化」という欺瞞
「家庭の問題」への矮小化は、日本社会の巧妙な責任回避システムです。
本来社会が担うべき支援責任を「家族の愛情」「家庭の責任」という美名のもとに個人に押し付け、構造的問題を不可視化してきました。
精神障害者の家族に焦点を当てるこの調査自体が、その構造を映し出しています。
本来問われるべきは「なぜ家族がこれほどの負担を強いられているのか」であり、「いかに社会的支援システムが機能不全に陥っているか」です。
PTSD/C-PTSDへの社会的無関心の暴力性
個人的に、日本のトラウマ支援の貧弱さは犯罪的とさえ言えると思います。
ベトナム帰還兵のPTSDを契機に体系的な支援を構築したアメリカと、
戦後の帰還兵を放置し、
家庭内の虐待・性暴力サバイバーへの支援も、極めて不十分な日本。
この差は偶然ではありません。
日本は一貫して、心的外傷・トラウマを、
- 「個人の心の弱さ」として処理し
- 加害構造を不問に付し
- 被害者に「回復の自己責任」を課して
そうして社会の責任ではないとしていました。
PTSD/C-PTSDが障害年金の対象外であることは、この社会がトラウマによる機能障害を「障害」として認めていないということです。
つまり、「加害の影響を社会的に承認していない」ともとれます。
問われているのは、わたしたち自身
冒頭の記事が示す2兆円超の損失。
これは氷山の一角に過ぎません。
- C-PTSDサバイバーへの支援不足が生み出す損失は?
- 貧困の連鎖が次世代に及ぼす影響は?
- 加害構造が不可視化され続けることの社会的コストは?
すべてを計算すれば、その額は想像を絶するでしょう。
わたしたちは問われています。
この社会を、強者だけが生き残る競争の場にするのか。
それとも、誰もが安心して生きられる共同体にするのか。
福祉を「お荷物」と呼ぶのか。
それとも「未来への投資」と位置づけるのか。
トラウマを「個人の弱さ」とするのか。
それとも「社会が承認し支援すべき障害」として認めるのか。
答えは、わたしたち一人ひとりの選択の中にあります。
民主主義社会において、主権者はわたしたちです。
この「社会という企業」の福利厚生を決めるのは、わたしたちです。
- PTSD/C-PTSDの障害年金対象化を求める声を
- 家族支援の充実を求める声を
- 福祉への投資拡大を求める声を
それぞれの立場から、声を上げることができます。
社会福祉への投資には、リターンしかない。
そのリターンを受け取るのは、わたしたち全員です。
今を生きるわたしたちも、まだ見ぬ未来の世代も。
あなたは、どんな社会で生きたいですか?
支援をお願いしています。
もしこのサイトに賛同して頂けるなら、よろしくお願いいたします。