⚠️【コンテンツ警告 / Content Warning】
この論考には、性的搾取・性暴力に関する記述が含まれます。
ご自身の状態に応じて、読むタイミングをご判断ください。
この記事でわかること:
✓ 当事者の語りがなぜ暴力になりうるのか
✓ 臨床語彙を用いた病理化ラベリングとは
✓ 「当事者だから正しい」という構造の危険性
✓ 語る者・聞く者それぞれに必要な倫理
✓ 「性的嗜好のゆがみ」という誤解が生む被害
これを読むにあたってまず聞いて欲しいことがある。
本当にこの問題を考えてほしい層、届いて欲しい人たちは、恐らく本稿について考えることをなおざりにする。けれどわたしはだからこそこの論考を執筆した。
本稿に共感し、言葉を慎重に選ぼうと思う人(あるいは言葉を紡ぐことに戸惑いを覚える人)は、既にこの問題に対する自覚がある。
だからそんなあなたは、主語を『私』と明確にして、言葉を紡ぐことを続けることを続けて欲しい。
言葉は人を傷つける。けれど自分を救い得る。
あなたの語りはあなたのものだ。あなたの語りはあなたのものだからこそ、価値がある。その語りの価値は主語が『私』だからこそのものだ。
SNSで発信することの恐怖や不安がより弱い立場の人たちにとっては常に大きな課題だ。その恐怖こそが、この論考にある問題である。
これは、あなたがあなたの語りを取り戻すためのわたしからの提案だ。あなたの語りはあなたの体験だからこそ、価値しかない。
当事者性は、ときに加害装置になる。
語りは救いにもなるが、沈黙を強制する武器にもなる。
沈黙を課されるのは、より脆弱な存在である。
今日はそうい話をしたい。
当事者性はなぜ暴力になるのか:当事者研究とそれを聞く者の倫理的責任――構造的暴力と表象の政治の分析
第1章 なぜ当事者の語りが暴力になるのか――構造的暴力としての当事者間格差
1. 当事者間の格差という問題
当事者研究は、もともと「語り得なかった経験を語ること」を通して、臨床の権力構造を可視化する試みとして始まった。
その核心には、支援者ー被支援者という一方向的な関係を問い直し、経験の主体性を当事者自身の側に取り戻すという目的があった。
しかし、この「語る力」の獲得が進むにつれて、今度は当事者間のあいだに新たな非対称性が生まれている。
社会的に評価される語り、メディアに受容されやすい語り、専門家との協働に資する語りが「模範的な当事者性」として流通し、それ以外の語りを周縁化する構造が形成されている。
このとき生じているのは、単なる人気や支持の差ではなく、構造的な承認格差である。
すなわち、どの当事者の声が「社会的に意味ある声」として、制度や支援に取り込まれるかを決める力が、当事者の外部ではなく内部に再配置されている。
2. 発言力が正義となる構造
この格差を支えるのは、「発言力=正当性」という構造である。
発言が社会的影響力を持つほど、それは「正しい」ものとして扱われ、
逆に、力のない発言は「信頼に値しない」ものとして扱われる。
こうした逆転は、権力が可視的な抑圧から、
象徴的支配の形式へと移行したことを意味する。〔引用:ブルデュー〕
発言力は単にフォロワー数や社会的知名度の問題ではない。
それは、「社会的に受け入れやすい苦しみ方」「説明可能なトラウマ」「専門家が理解できる語り方」などの表象の様式によって分配される。
その結果、逸脱した語りや矛盾を抱えた語り、怒りを含む語りは、「危険」「加害的」「治療的でない」とみなされ、支援の対象から排除される。
こうした排除は、当事者コミュニティの内部でさえ「安全」や「支援」を名目に正当化される。
つまり、「安全な場」を確保するために、「危険な語り」をする当事者を排除するという構造である。
このとき、暴力は直接的な攻撃としてではなく、善意による排除として実現する。〔引用:ガルトゥング〕
3. 語りの逸脱と構造的排除
当事者間における排除の過程を観察すると、
次のような段階が見られる。
1. 語りの規範化
特定の語り方や感情表現が「正しい回復のあり方」として共有される。
「聞き手の安心を優先し、理解しやすく整理された苦しみ」それが模範的当事者性である。
2. 逸脱の発見
その規範に合致しない語り――怒り・矛盾・攻撃的表現・沈黙など――が「逸脱」として認識される。
3. 危険性のラベリング
逸脱する語りは「加害的」「他者を傷つける」とされ、安全の名のもとに排除の対象となる。
4. 共同体的排除
影響力のある当事者の呼びかけや発言を通して、逸脱した語り手がコミュニティ全体から切り離される。
この過程では、排除の根拠が常に倫理やケアの語彙で説明される点が重要である。
つまり、暴力は「悪意」ではなく、「正しさ」によって正当化される。
結果として、暴力を行使している当人もまた、自らを「守る側」「ケアする側」として認識している。
4. 「語る権利」の非対称性
この構造の本質は、「語る権利」が平等に保証されていない点にある。
当事者研究が「誰もが語れる場」であるとされながら、
実際には、「どの語りが信じられるか」が社会的に選別されている。
その選別は、個々の語り手の意図とは無関係に、社会的承認の制度のなかで行われる。
この非対称性を当事者自身が認識しないかぎり、「語る」という行為は容易に暴力の回路となる。
語りが他者の沈黙の上に成り立っていることで、沈黙がときに抵抗の形式であることを理解しなければならない。〔引用:バトラー〕
5. 小結
本章では、当事者間に生じる格差を「構造的暴力」として位置づけた。
この暴力は、個人の悪意や競争心から生じるものではなく、語りの制度的承認構造に内在している。
語ること自体が「正義」の形式を帯びるとき、その語りは他者の声を消す装置として働く。
次章では、この構造を支える検証不能性の問題を分析し、なぜ語りが「真実」として固定されるのかを明らかにする。
第2章 「当事者が言うから正しい」の危険性――検証不能性の装置
1. 「真実」としての語りの成立
当事者研究や回復ナラティヴの運動において、「語ること」は治療的・政治的行為の両義性を帯びてきた。
語りは自己の経験を再構成し、他者と共有可能な形式に翻訳する行為であり、その過程自体が主体の回復とされてきた。
しかし、語りが社会的に受容されるためには、「真実らしさ」という形式が必要とされる。
この「真実らしさ」は、語り手の倫理性、整合性、語りの文体や表現形式によって構築されるものであり、経験そのものの真実とは異なる。
つまり、社会的に評価される語りとは、理解されやすい苦しみの形式である。
このとき、語りの「真実」は内容にではなく、伝達可能性と信頼性の印象に基づいて承認される。
語りの整合性、感情の抑制、反省的な自己像といった記号が、「誠実さ」や「成熟」といった徳目に結びつけられ、「信じられる語り」を構成する。
その結果、語りの受容は内容の検証ではなく、語り手の社会的印象の評価に依存する。〔引用:ゴッフマン〕
2. 検証不能性の構造
この「印象の信頼」によって成り立つ関係には、決定的な問題がある。
それは、受け取る側が語りを検証できないという事実である。
トラウマや精神的苦痛といった領域では、経験の内実が客観的に測定できないため、語りは原理的に不可視の出来事への証言として位置づけられる。
このとき、受け手は語りの真偽を判断する手段を持たない。
ゆえに、語りを受け取る際の基本的態度は、「信じるか/信じないか」の二項対立に還元されやすい。
そして、社会的に影響力をもつ当事者の語りは、その権威性ゆえに「信じるべきもの」として前提化される。
こうして、「検証できないが信じられる語り」が量産される。
それは信仰的な構造を持ち、語りの内容よりも語り手の位置とイメージによって支えられる。
ここにおいて、語りの「真実性」は epistemological(認識論的)な問題ではなく、社会的装置の問題となる。
3. 異論が排除されるメカニズム
検証不能性の社会的帰結として最も顕著なのは、異論の排除が語りの正当性とは無関係に進むという事態である。
当事者コミュニティ内で、ある影響力のある発言が批判を受けたとき、その批判の内容ではなく、批判者の態度や語り方が問題化される傾向がある。
「言い方が攻撃的だった」「感情的すぎる」「相手を傷つけた可能性がある」――
こうした言葉によって、異論を呈した者が「不適切な振る舞いをした人」として排除される。
このとき、排除の根拠は意見の妥当性ではなく、道徳的印象操作に基づいている。
重要なのは、こうした非難があくまで「安全」や「共感」「配慮」といったポジティブな語彙のもとで行われる点である。
つまり、暴力的な排除は「善意の形式」で進行する。
批判的な当事者は「他者への配慮を欠いた危険人物」として扱われ、その発言の意図や論点そのものは議論の俎上に載らない。
この過程では、発言内容の検証が停止し、代わりに態度の印象評価が共同体の倫理的判断を支配する。
つまり、何が「危険」かを決めるのは、意見の中身ではなく、
その人が「どう見えたか」「どう感じられたか」である。
ときにそれは、「自己愛の強い人」「理想化と脱価値化を繰り返す人」など、
臨床的ラベルを援用した新たな(病的)スティグマとして現れる。
このとき、異論を唱えた当事者は、単なる意見の異なる他者ではなく、心理的に欠陥のある存在として再定義される。
こうして暴力は、道徳的評価から臨床的診断へと形を変え、当事者のあいだに「臨床の言葉を使った排除」という新しい統制様式を生み出す。
第三章 当事者が臨床を語るときの倫理と受信者の責任
1. 当事者が語る「臨床」の特異性
当事者が臨床を語るとき、その言葉は単なる「私的体験の記述」にとどまらない。
そこには、自らの経験を社会的言語へと翻訳し、他者の理解を媒介しようとする意志が含まれる。したがって、その語りは常に主観的経験と社会的知との交点に位置する。
この特異な位置づけゆえに、当事者の語りはしばしば「真実」と「臨床知」とのあいだで曖昧な位置を取る。
当事者の語りが社会的権威を帯びた瞬間、それはもはや個人的言説ではなく、
研究的言説(knowledge production)として社会的効力を持ち始める。
ゆえに、当事者が臨床を語るときには、暗黙のうちに研究者・専門職に課される倫理的責任が発生していると考えられる。
2. 語り手の倫理:臨床語彙の暴力化を防ぐために
当事者が臨床の言葉を用いるとき、その言葉は経験の翻訳手段であると同時に、他者を分類しうる力を持つ。
この力が無自覚に使われると、当事者間においても「診断の言葉による排除」が生じうる。
語り手に求められる倫理は、以下の4点に要約される。
1. 他者の語りを診断的に解釈しないこと
臨床概念は、相手の言葉を「理解したつもり」にさせる危険をはらむ。
理解とは支配の一形態になりうることを常に意識する必要がある。
2. 「支援」や「理解」を名目とした介入を慎重に扱うこと
善意の言葉が、相手の主体性を奪うことがある。
臨床語彙を用いるときには、必ず「相手の経験の独自性」を優先する。
3. 自らの言葉の社会的影響力を自覚すること
フォロワーや読者を持つ当事者は、その発言が共同体の判断を方向づけうる立場にある。
その影響力を自覚せずに「危険」「加害的」などの語を用いることは、構造的暴力の再生産に加担する。
4. 主語を明確に『私』とすること
「私は~と感じた」「私には~が難しかった」と表現することで、語りを経験の範囲にとどめることができる。
しかし、「私は“虐待サバイバーには~が多い”と考える」のように、入れ子構造によって他者を一般化する語りは、主語が「私」であっても暴力的な機能を持つ。
「私」という形式を用いながら、他者を説明・規定する構文には、経験の翻訳が他者の支配に変わる危険が潜む。
倫理的語りとは、「誰を説明しているか」を常に自問する行為である。
語り手の倫理とは、臨床語彙を武器にしないこと、
そして何よりも、他者を語りの素材にしない勇気をもつことである。
3. 受信者の倫理:検証不能性を生まないために
発言者の倫理がいかに保たれても、受け取り手の側に倫理がなければ、構造的暴力は止まらない。
特に当事者コミュニティにおいては、「影響力のある語り手の言葉」が容易に共同体の“真理”として受け取られる。
このとき、受け取り手は自らの共感や同調を検証の代替物として用いる。
受信者に求められる倫理は、次のように整理できる。
1. 情報を検証する姿勢を持つこと
「この人が言うから正しい」ではなく、「どのような前提で語られているか」を問う。
2. 有名な当事者の言葉=正義とみなさないこと
社会的承認やフォロワー数は、倫理的正当性を保証しない。
3. 同調圧力によって他者を沈黙させないこと
「危険」「排除すべき」といった語が生まれたとき、それが誰の安全を守り、誰の声を奪うのかを立ち止まって考える。
このように、受信者の倫理とは、発言者の言葉を一つの経験の表明として聴く態度であり、
「診断」でも「正義」でもなく、「対話の入口」として受け止める姿勢である。
4. 構造的暴力を再生産しないために
当事者コミュニティにおける暴力は、しばしば善意の形をとって現れる。
「支援」「啓発」「臨床的理解」といった名目が、暴力の正当化装置となる。
したがって、構造的暴力を止めるための第一歩は、自らの善意を疑うことである。
語り手は「誰かを守るため」という言葉を慎重に使い、
受け取り手は「守られるべき人」と「排除される人」を分ける構造に加担しない。
臨床語彙や倫理的言説を盾に、他者の存在を矮小化することこそ、最も見えにくい暴力のかたちである。
善意は暴力になりうる。
だから、私たちはまず自らの善意を疑わなければならない。
第四章 倫理とは関係の形式である
倫理とは、単なる道徳規範や行動規則ではない。
それは、人が他者と共に生きる際に生まれる関係の形式であり、共同体の中で互いに応答し合う責任の構造である。
この「関係の形式としての倫理」という視点が失われたとき、社会は容易に暴力的な秩序へと転化する。
現代社会では、「法律は守るべきルールである」という理解が支配的である。
だが、法とは本来、倫理の最低限に罰則を与えたものに過ぎない。
つまり、法律が存在する以前に、そこには「人が人を傷つけてはならない」「他者を踏みにじってはならない」という倫理的な感覚が先立っている。
それを欠いた法は、形式的な支配装置となり、人権を守るどころか、むしろ人権を侵す力として機能しうる。
倫理を「押し付け」とみなす風潮が、現代にはある。
ある当事者は私にこう語った。「倫理は人に押し付けられるものではない」と。
確かに、倫理は外部から強制される規範ではない。
だが、他者と共に生きる限り、私たちは必然的に何らかの関係の中にあり、その関係において互いに責任を負っている。
倫理とは、その「責任の形式」そのものである。
倫理を「押し付け」として退ける社会は、他者との関係を断ち切り、責任の共有を拒む社会である。
そこでは他者はもはや「他者」として現れず、ただの対象や情報として処理される。
虐待サバイバーたちの現実を見れば明らかである。
彼らは違法とされる行為に晒されながらも、しばしば犯罪被害者としては扱われない。
そこにあるのは、法の不在ではなく、倫理の不在である。
彼らが受けた暴力は、形式的な襲撃としての犯罪ではなく、倫理の不在による関係の崩壊から生じた。
倫理の不在とは、他者を人間として扱う責任を放棄することだ。
その放棄こそが、彼らを最も深く傷つけてきたのである。
そして皮肉なことに、倫理の不在によって苦痛を味わった者が、
やがて他者に対して、自らの倫理観の欠如を正当化してしまうことがある。
それは矛盾であると同時に、極めて人間的な現象でもある。
倫理の断絶は、個人の悪意ではなく、構造的に連鎖する。
倫理を奪われた社会では、人は加害と被害の区別を失い、
関係そのものが暴力の回路として再生産されてしまう。
倫理とは、他者の痛みに応答する力である。
それは、「あなたはそこにいる」と言い続ける行為であり、
沈黙させられた声に耳を傾けるという不断の実践である。
この応答の責任を放棄したとき、社会は構造的暴力へと転化する。
暴力とは、倫理の不在が制度化された状態なのだ。
倫理とは、共同体で生きることの責任である。
それは、他者の存在に対して絶えず応答しつづける、終わりのない営みである。
法や制度は、その応答の形式を一部だけ可視化したものに過ぎない。
だからこそ、私はこう結ぶ。
倫理なき社会には、人権は存在できない。
なぜなら、人権とは、人を人として扱うという倫理的約束の上にしか成り立たないからである。
倫理の欠如した社会では、人権は理念ではなく、特権へと変質する。
そしてそのとき、社会はもはや人間の共同体ではなくなる。
そして、
倫理なき関係は、関係ではなく支配である。
支配は必ず、語り得る者と沈黙させられる者を分断する。
その瞬間、当事者性は暴力装置へと転化する。
補記:この論考を書くに至った経緯
この論考は、私自身が当事者の語りをめぐる暴力的な構造に巻き込まれた経験を出発点としている。
私が見たのは、ある種の「臨床的語り」が、他者の人格や性的嗜好を病理化し、
正義の名のもとに他者を沈黙させる過程だった。
SNS上で、私の発言や立場を知らぬままに、
「理想化と脱価値化の振れ幅が強い」「自己愛傾向が強い」といった専門用語が投げかけられた。
それらは臨床言語の形をしていながら、私という個人の語りを封じる装置として作用した。
とりわけ「性的嗜好のゆがみ」という言葉が発せられたとき、その痛みは、私自身の人格や尊厳に直接触れるものであった。
この表現は、私の性的嗜好や欲望を「トラウマの結果」「逸脱」とみなすことで、私の生の意味づけを他者の臨床的視点に奪われるものだった。
私はそれに抗議するため、
そして、こうした構造がいかにして生まれ、どのように再生産されるのかを明らかにするために、この論考を書いている。
私の意図は、誰かを攻撃することではない。
私が目にしたのは、善意の言葉がどのように暴力へと変わるかという「構造」である。
それを記述することこそ、再び誰かが同じ傷を負わないために必要な行為だと信じている。
この論考が、当事者が臨床を語るときに求められる倫理、
そして受け取る側が負うべき責任について、
小さな一石となることを願っている。
これは譲らない。譲ってはいけない。
いまだ(私の知る限りでは)訂正がされない、当事者語りの暴力を、明示しなければならない。
この論考の最大の(個人的な)目的はそこにある。
そして――この痛みが、私を筆を執らせたのだ。
付録:「性的嗜好のゆがみ」というラベリングの暴力性――言葉が奪うもの
この章は、私自身の経験をもとに記す。
分析ではない。
ここに記されるのは、私が実際に受け取った言葉と、それによって失われかけた私自身の声の記録である。
この出来事を語ることは、誰かを糾弾するためではなく、
「言葉がどのように暴力となるか」を明示するためである。
1. ラベリングが生む二次被害
> 「虐待サバイバー(複雑性PTSD)に風俗嬢やSM嬢が多いのは、虐待被害によって性的嗜好が“ゆがむ”からなのだと思います。」
この言葉を、私は否定し続けなければならない。
なぜなら、その渦中にいた頃の私は、これを否定するだけの自己価値を持ち合わせていなかったからだ。
私は、対価として金銭を受け取ることさえできないほどに、自分の価値を感じていなかった。
性的に搾取されることに抗うこともなく、むしろ率先して搾取されていた。
暴力的な性的行為を望んで受けているようにしか見えなかった私に、彼らは言った。
「被虐癖」「ドM」
「レイプされて被虐に目覚めたんだ?」
当時の私には、その言葉に抵抗する術がなかった。
そうだと頷く以外の選択肢を、思いつくことすらできなかった。
けれど、本当はわかっていた。
――望んでいるように見えても、それは欲求ではなかった。
私はある時期から、自分を傷つけようとする意図が確かにあることに気づき始めていた。
それでも長らく、自分の自己価値の不在、主体性の欠如を理解することはできなかった。
「これは私が自分で選択しているのだ」と思い込むことでしか、世界との関係を維持できなかったのだ。
自分さえ維持することが不可能だったのだ。
そうではないかもしれない――そう気づけたとき、ようやく私は、回復のスタートラインに立つことができた。
あのラベリングは回復への道のりを妨げる。なぜならその言葉には「自分の選択」という意味があるからだ。
2. 「ゆがみ」という言葉がもたらす構造的暴力
「性的嗜好がゆがむ」という表現は、何を意味しているのか。
「ゆがむ」という言葉は、本来あるべき“正常”な形から逸脱するという含意を持つ。
つまりこの語は、性的搾取のど真ん中にいた人々を、
「正常から逸脱した嗜好をもつ人」として位置づける。
それは、被害の本質を「個人の特性」に還元することで、構造的な加害性を不可視化する装置である。
すなわち、「構造によって生じた損傷」を「個人の嗜好」として再ラベリングする暴力だ。
性的搾取を受けた人が、その後も搾取的な環境に身を置いたり、自己価値を欠いたまま性的関係を持ったりすることは、確かにしばしば観察される現象である。
しかし、それを「性的嗜好のゆがみ」と呼ぶことは、被害者の生を病理の物語に閉じ込めてしまう。
それは嗜好ではない。選択ではない。
それは、長期かつ反復的な虐待によって形成された自己価値の完全否定であり、「自分には、対価を受け取る価値もない」「尊重される資格もない」という、深刻な認知の陰性変化である。
したがって、それは「ゆがんだ嗜好」ではなく、「陰性変化を強いられた認知」と呼ぶべきものなのだ。
3. 当事者の声――削除されなかった批判
以下は、私が実際に発した言葉である。
私が、その構造を、医療的な支援も心理的な補助もないままに、どうにか抜け出して獲得した「自分の言葉」である。
地獄からようやく抜け出して、取り戻した自己評価の声だ。
>「それを個人の“被虐嗜好”と呼ぶのは乱暴ではないでしょうか。
私は金銭という対価さえ頂けないほどに歪み切った価値観を持っていましたが、それを“歪んだ嗜好”と呼ばれることがどれほど自尊心を傷つけるか。
歪んでいるのではなく、陰性変化を強いられたのです。
治療的な場面では、もっと寄り添った言葉が必要だと思います。
心的外傷の影響を“被虐嗜好”と呼ばれるのは堪らない。
そのラベリングをするのは、私たちを搾取し加害的に関わる人たちだけで十分です。
深刻な心的外傷による陰性変化に対して、治療者には慎重に言葉を選んでほしい。
これ以上、私たちを誤解するような説明はされたくない。これは本当に切実な思いです。」
>「“被虐嗜好”ではないのです。そこによろこびを見出しているのではありません。
陰性変化を強いられた当事者への不当なラベルだと思います。
試し行動への不当な評価と同じように、“性的嗜好のゆがみ”という評価は不当ではありませんか。私は被虐されることを本当は望んでいません。欲しかったのは、まったく別のものです。
“被虐嗜好”であるかのように見える当事者の行動(変化)を、マゾ的欲求として主体を当事者に置くことは、加害者や搾取者によるラベリングと同じです。」
4.加害行為の正当化と搾取の再生産
これは、当事者の語る臨床があたえる最も深刻な影響だろう。
わたしの経験にもある通り、加害的な関係にあった相手は「性虐待(性暴力)の影響で被虐に目覚めた」という自分にとって都合の良いストーリーを採用する。
加害行為を正当化するために、搾取を継続させるために、搾取構造の一端を被害者の責任だと主張したがる。
そのとき、この発言が採用されかねない。既に実際に採用されている。
そして別の当事者の語りによってさらに補強されるのだ。
当事者の語りを真に受けた誰かが、それを根拠に別の当事者での搾取の構造を再生産する。
当事者の語りが、別の当事者を搾取の構造に閉じ込める。
その当事者に言い聞かせられるのは、とある当事者の語りとしての:
「お前は機能不全の家庭にあった。だからこうされることが好きなんだ(被虐嗜好にあるんだ)」
この付録は、理論の外側に置かれる。
それは「理論の補強」ではなく、倫理の回復のための証言である。
倫理のない社会には、人権は存在できない。
だから私は、ここにこの言葉を残す。
もう誰も、この言葉で傷つけられないように。
語りの届き方――当事者間の権力勾配について
私のアカウントの発言力は、彼女のそれと比べれば10分の1ほどだろうか。
フォロワーの数でそう言えるが、拡散力という点で言えば、その差はさらに広がるだろう。
発言力の高さとは、すなわち社会への影響力だ。
当事者の語りが、たとえ「個人的な論考」として発せられたものであっても、それが「当事者の声」として社会に受け取られるなら、その影響は、他の当事者の理解や評価を直接的に変えてしまう。
彼女が「虐待被害によって性的嗜好がゆがむ」と語ったとき、それは「彼女の私見」ではなく、“当事者による証言”として社会に流通した。
その語りは、他の多くの被害者像をも、同じ枠の中に押し込める。
一方で、実際にその地獄をくぐり抜けて、回復の途中にいる者の声は届きにくい。
なぜなら、それは痛みをともない、断定を避け、単純化されにくいものだからだ。
社会は「わかりやすい言葉」を求め、複雑な現実を語る声には耳を傾けにくい。
こうして、「発信力のある当事者」と「届かない当事者」のあいだには、
新たな階層的差異――当事者間の権力勾配が生まれる。
この構造こそ、私が問題にしたいことの核心である。
影響力をもつ者の語りは、社会の眼差しを変える力をもつ。
だからこそ、その語りに倫理が問われなければならない。
彼女は、たった一度それを語るだけで、社会に届く。
私は、同じことを否定するために、何度も、何度も、くり返し語り続けなければならない。
――それがどれほど不均衡なことか。
そして、その繰り返しこそが、声を失わないための抵抗なのだ。
「いいね」の暴力——倫理なき承認の構造
もしかしたら、
「それはまだ社会的に認められた理論ではない」
「学問的に証明されていないのだから、議論の対象にすぎない」
そうやって、問題を矮小化しようとする人がいるかもしれない。
けれど、このラベリングによる暴力は、すでに機能しているのだ。
SNS上で発信されたその言葉は、誰かのタイムラインに流れ、「なるほどね」と思った人が「いいね」を押す。共感した誰かが「リポスト」をする。
それは単なる行為ではない。
その一つ一つの「いいね」や「リポスト」が、
その当事者を誤解した人の数である可能性を、
――静かに、けれど確実に示しているのだ。
その数字を見たときの当事者の気持ちが、あなたには想像できるだろうか?
わたしという状態に、性的搾取に身を置かざるを得なくなった心理構造への誤解――加害的関わりをしてきた者たち、性的搾取者と同じラベリングをされる――が、数字として可視化される。
見なければいい?
では、誤解した人たちはいつ、正確な情報に触れる?
その損害は未知数だ。なぜなら彼らはそれを自身で検証し得ないからこそ、その投稿内容にいいねという反応を残しているのだ。
その「なるほどね」の根拠は、いったい何なのだろう?
その人が「当事者」だからではないのか?
その当事者の語った内容に、本当の理解があったのか?
「当事者がそう言うならそうなのだろう」という思考停止のうえに置かれた、安易な納得だったのではないか?
「当事者」というラベルは、語りに特権を与える。
けれど、それは時に、語りの責任を奪うことにもなる。
その人が“当事者”であるという事実が、語りの妥当性の根拠になってしまうのだ。
違う!
そう叫んでも、その投稿の先にいる人たちに、その声は届かない。
「いいね」の波にかき消されて、私の声は拡散されない。
誰も訂正しないまま、その投稿だけが「事実」として独り歩きを始める。
この構造そのものが、
すでに倫理の崩壊であり、
沈黙を再生産するシステムなのだ。
だからこそ、私は問う。
――当事者の臨床語りにおける倫理を。
語りの力があるなら、その力の意味を。
言葉を投げるなら、その着弾点を。
それを、誰かの傷口に落とす前に。
終章 沈黙のあとで
語りとは、常に危うい行為である。
それは、自らの傷を言葉という共有可能な形に変換し、他者に手渡す行為だ。
だがその瞬間、語りはもう「私のもの」ではなくなる。
他者の解釈の中で、時に誤用され、暴力として再生産される。
だからこそ、語りには倫理が必要なのだ。
そして、聞く者の頷きには責任がある。
語る者の言葉には、他者を沈黙させない慎みが求められる。
私がここに書いたのは、痛みの報告ではなく、倫理への祈りである。
語りが他者を傷つけることのないように。
そして、沈黙が誰かの居場所を奪うことのないように。
沈黙のあとで、語りは再びはじまる。
そのとき、どうか思い出してほしい。
――語りには、倫理が必要なのだ。
「応答可能性(responsibility)」は、「責任(responsibility)」と同根の言葉である。
つまり、暴力の反対は沈黙ではなく、応答である。
そして応答は、真実を決めることではなく、他者の痛みに対して開かれ続けることだ。
当事者語りに耳を傾けることをしようとした人たちに、話を聞く当事者の選別という残酷な行いの意味を知ってほしい。
あなたが耳を塞ぐこと、
あなたが聞きたい話だけを聞くことは、
本当の意味で当事者への理解となるのか?
あなたは無関心でいたくなかった人ではなかったのか?
その善意の意味を問い直そう。
【関連論考】この出来事で見られた「第三者の暴力」の構造については、「日本社会における『謝罪の儀式』と正義の不在」で詳しく分析しています。

2025年11月4日 (火) Copyright © ハココ@WLTOS
無断転載・複製禁止、
出典を明記した上での引用のみ許可します。

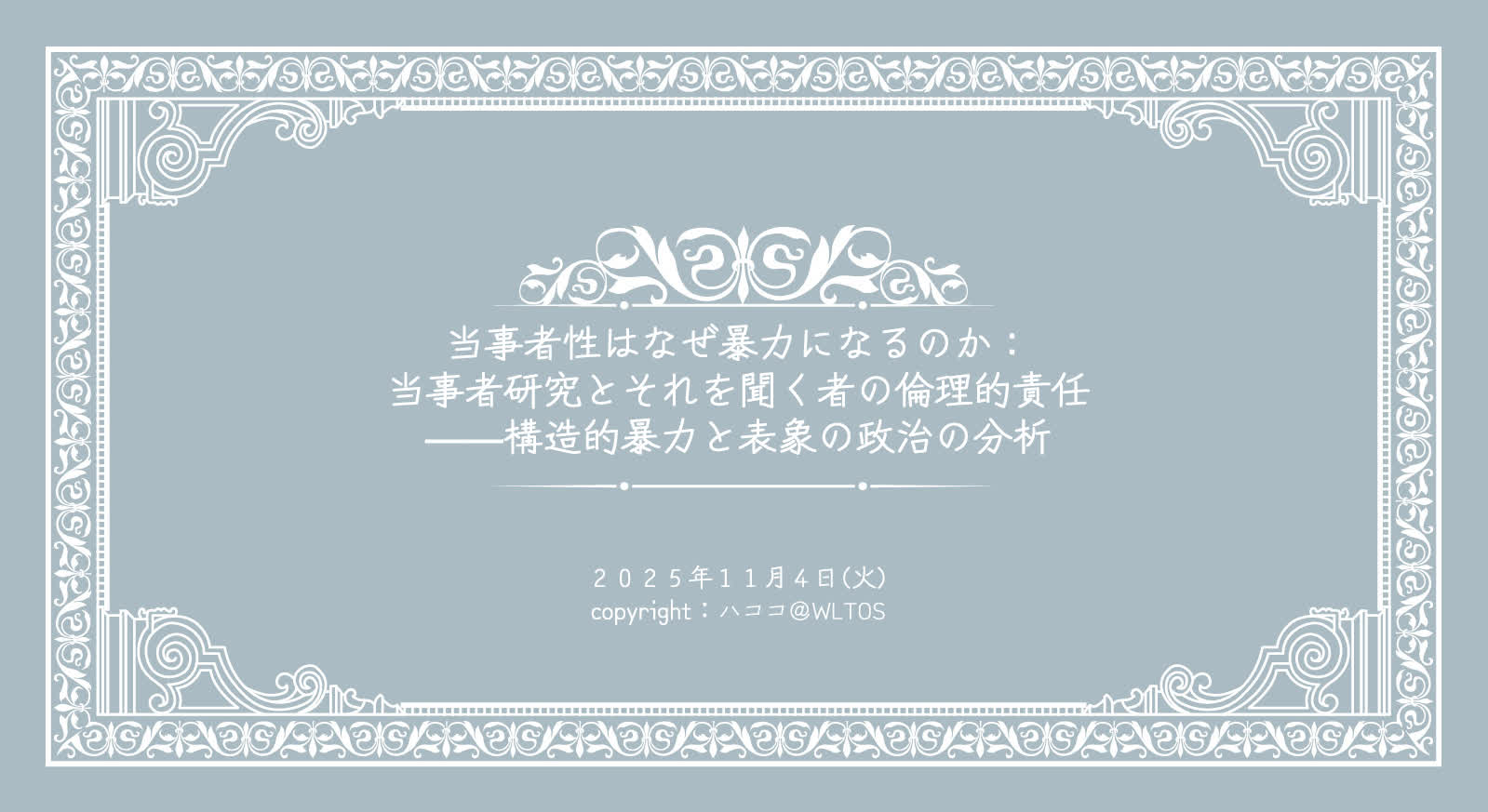
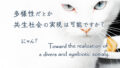

コメント